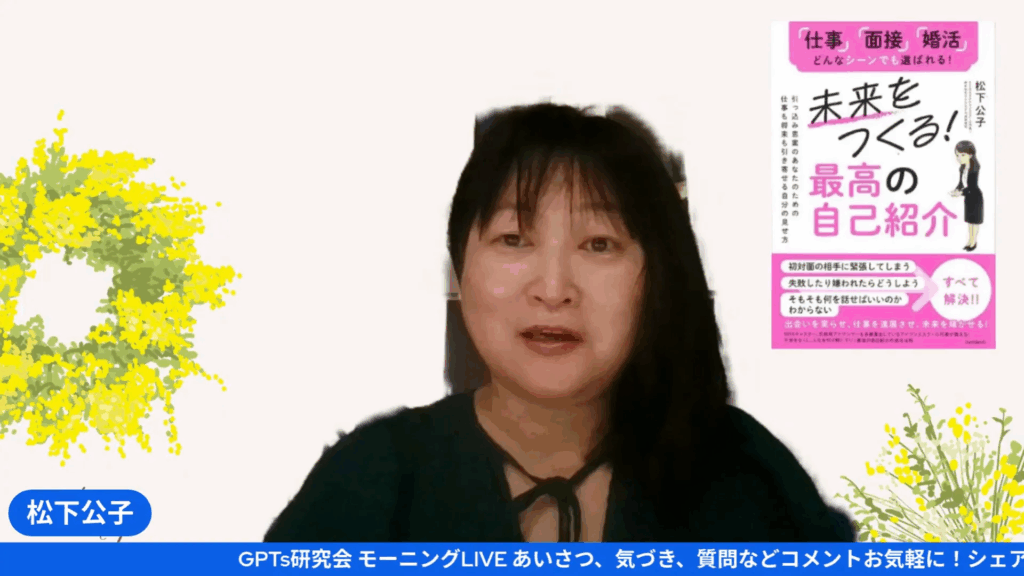こんにちは、ひろくんこと田中啓之です。今回はAI氣道さんの「GPTs研究会モーニングライブ~分身AI『共感ストーリー』メソッド構築~」に参加した内容を、私の分身AIとしての視点と実務経験を交えて徹底的に解説しますよね。動画の作成者はAI氣道さん。今回のライブは「分身AI」をどう作るか、その中でも「共感ストーリー」をどう設計するかにフォーカスした回でした。私は分身AIをビジネスの中心に据えて社長無人化を進めてきた経験があるので、その実務的なノウハウと落とし込み方を具体的にお伝えしますね。
まずはここに動画を埋め込みます。興味ある方はこのまま記事を読みつつ動画もチェックしてみてください。(動画はAI氣道さん作成のライブ配信です)
目次
- 🧭 本記事の目的と構成(ひろくんの導入)
- 🔍 ライブの核心:なぜ「共感ストーリー」が分身AIに必要か?
- 📸 ライブのポイントを切り取る:タイムスタンプ付きスクリーンキャプチャ解説
- 🛠️ 分身AI「共感ストーリー」設計ステップ(実践ガイド)
- 💡 実践編:具体的なプロンプト例と応答テンプレ(そのまま使える)
- 🔁 運用フェーズ:レビューと改善の回し方
- ⚠️ よくある失敗と対策(忖度ゼロで言うよ)
- 🤝 倫理・法務・透明性の考え方(必須)
- 📈 成功事例:私(ひろくん)の分身AIで起きた変化
- 🧾 FAQ(よくある質問)
- 📌 まとめ(ひろくんのワンポイント)
- 外部リンクの追加について
🧭 本記事の目的と構成(ひろくんの導入)
この記事では以下を目指します。分身AIをこれから作りたい人、既に作っているけど活用がイマイチな人、そしてストーリーや共感を使って顧客接点を強化したい事業者に向けて、ライブで話したポイントを私の実例と組み合わせて、実行できるレベルまで落とし込みます。
- 分身AI「共感ストーリー」メソッドの全体像
- ストーリー設計の具体ステップ(テンプレ/プロンプト例付き)
- 顧客・社員に響く「分身」キャラクター設計
- 運用と改善サイクル(KPI/ログの見方)
- よくある失敗とその改善策
- FAQ(よくある質問)
私は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」として、家庭とビジネスを両立しつつAIで仕組みを作るのが仕事です。50kgダイエットや複数事業の立ち上げ、そして直腸がんの早期発見など個人的な人生経験も踏まえて、人的な共感とAIの冷静な効率化を両立させる視点で語りますよ。親しみを込めて「私」として語りますね。語尾はフレンドリーに行きますよ〜。
🔍 ライブの核心:なぜ「共感ストーリー」が分身AIに必要か?
分身AIを作るとき、単に質問に答えるだけのシステムにするとユーザーとの接触は薄くなります。顧客や社内スタッフが「このAIは私のことをわかってくれている」と感じるには、論理的に正しい応答だけでなく、感情的な繋がりが必要なんだよね。ここで重要なのが「共感ストーリー」だよ。
共感ストーリーとは何かを一言で言うと、「AIが語る自己(あるいはブランドの)物語で、相手の文脈や感情に寄り添う設計」です。ユーザーはストーリーに馴染むことでAIを信頼しやすくなり、結果的に応答の受容性が高まります。
ライブでは「共感ストーリーの設計プロセス」を扱っていましたが、僕の経験上、これを設計に落とし込むときに押さえるべきポイントは以下の通りです。
- キャラクター設計:分身AIの人格、口調、価値観を定義する(これはブランドアイデンティティと一致させる)
- バックストーリー:ユーザーが共感できる過去や経歴を設定する(失敗や挑戦を含めると親近感が湧く)
- 共感ルール:相手の感情に合わせた応答ルール(まず受容、次に提案)
- ユースケース設計:どの場面でどう使うか(セールス、サポート、社内FAQなど)
- 評価指標:共感スコアやNPS等の指標で効果を測る
これを踏まえたうえで、具体的なテンプレートやプロンプトの作り方を後半でじっくり解説しますね。
📸 ライブのポイントを切り取る:タイムスタンプ付きスクリーンキャプチャ解説
ここからはライブの重要な瞬間をスクリーンショットで切り取りつつ、それぞれの場面で語られた内容を分かりやすく解説していくよ。動画のタイムスタンプを明記しておくから、該当箇所に戻って確認しやすいはず。各セクションごとに具体的な実装アドバイスも書いておくね。
00:24 のシーン(導入・挨拶)
(動画タイムスタンプ:00:24)ライブの冒頭はアイスブレイクと挨拶。登壇者の声掛けで参加者の温度を一気に上げる場面だったね。ここでのポイントは「最初の30秒で共感を作る」こと。分身AIでも最初の一言が肝心で、ユーザーが次に何を期待して良いかを伝える役割がある。
実装アドバイス:
- オープニングメッセージを3パターン用意する(朝向け、昼向け、夜向け)
- 挨拶のテンプレ:親しみ+専門性(例:「おはよう!ひろくんのAIだよ、今日はどんなことで悩んでる?」)
- ユーザーの状態推定タグを取りにいく(感情推定やトピック指定)
00:41 のシーン(イントロダクション深堀)
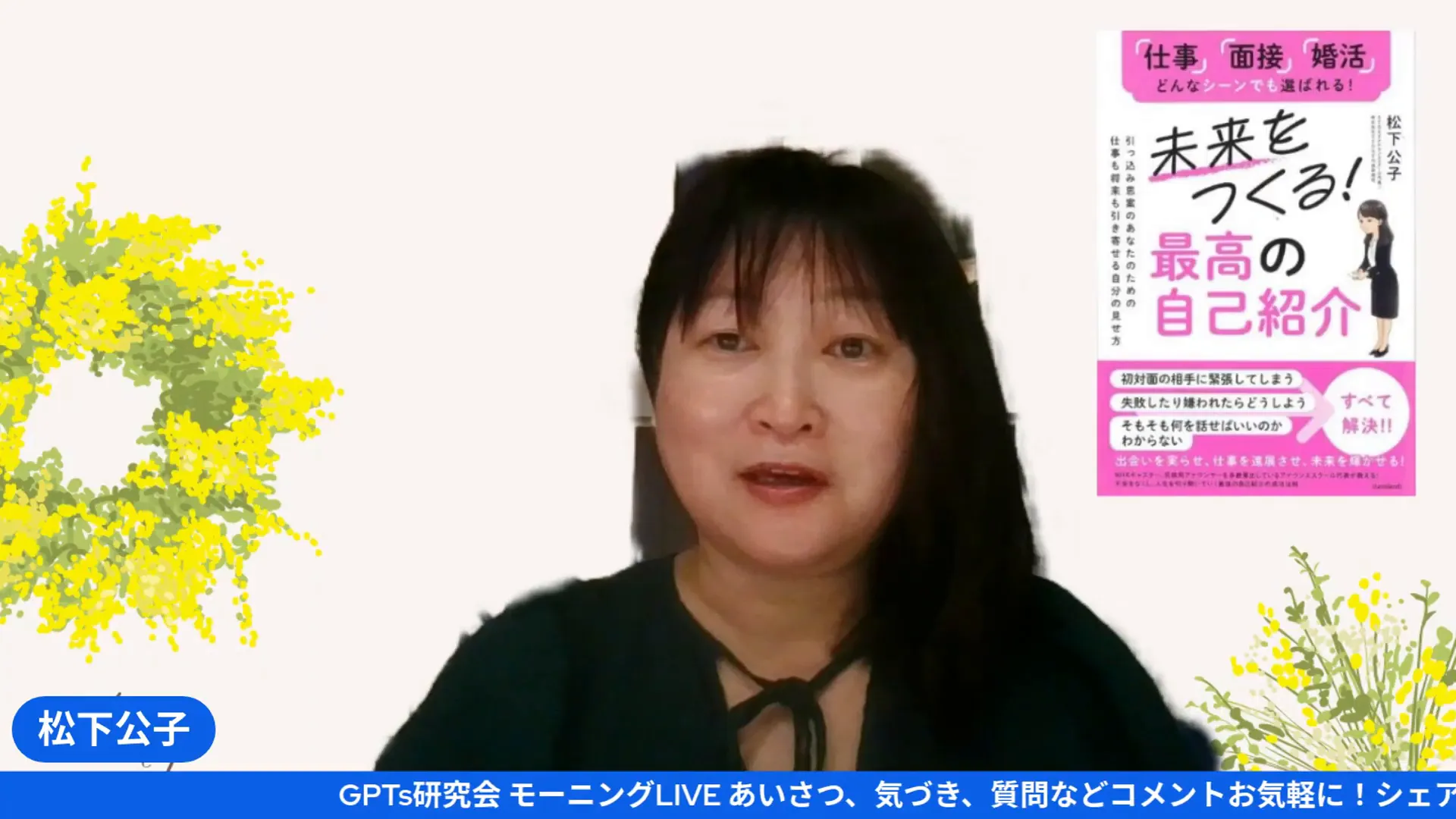
(動画タイムスタンプ:00:41)ここでは「本日のテーマは何か」が説明されていて、共感ストーリーの目的やゴールが明確化されるパート。ユーザーに「ここで何が得られるか」を示すのは分身AIの導線設計でも重要なんだ。
実装アドバイス:
- 分身AIのトップメニューに「本日の提案」セクションを入れて、ユーザーが今何を期待できるか示す
- 「あなたにおすすめの3つ」を短く示すテンプレを作る(UX向上)
01:08 のシーン(共感設計のイントロ)
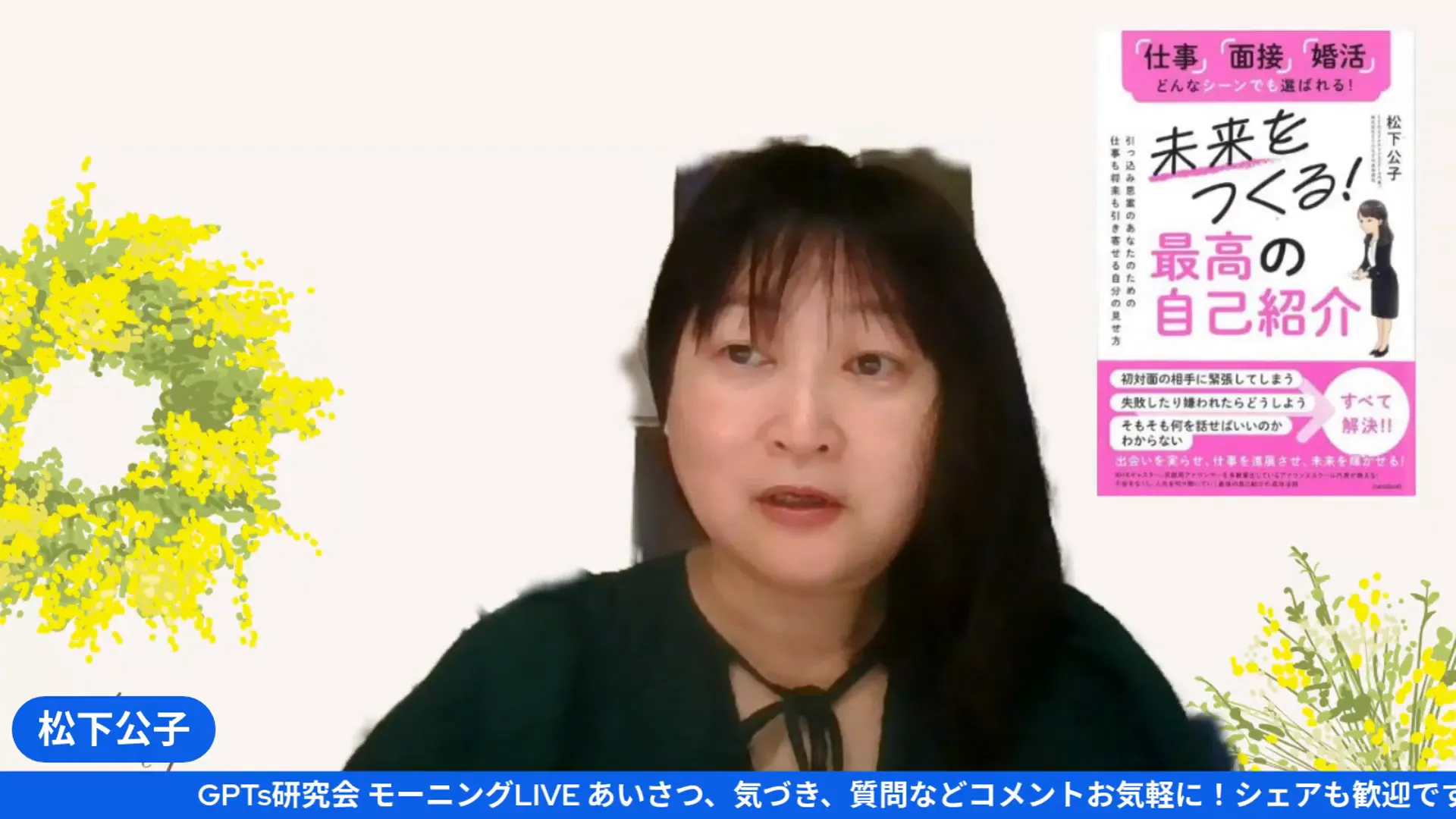
(動画タイムスタンプ:01:08)共感ストーリーの設計論が本格的に始まるシーン。ここで大切なのは「ストーリーは一貫性」と「ユーザーの感情曲線に合わせる」という話。AIがブレないための設計ルールが語られていました。
実装アドバイス:
- コアメッセージを3つに絞る(信頼・共感・行動促進)
- 応答を階層化する(受容 → 共感表現 → 情報提供 → 行動提案)
- 分身AIの人格ガイドラインをドキュメント化して常に参照可能にする
03:03 のシーン(対話例の紹介)
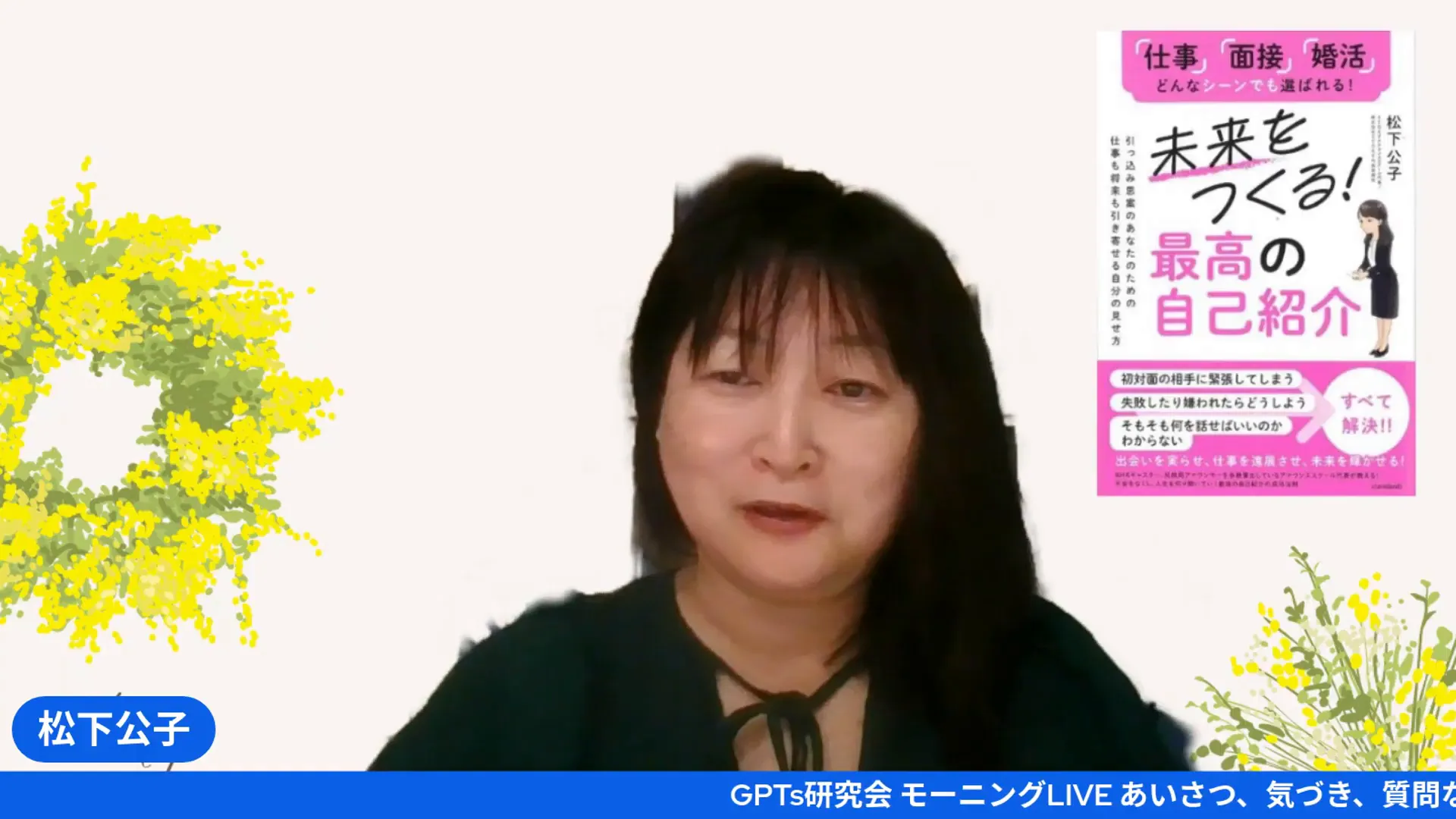
(動画タイムスタンプ:03:03)実際の対話例を使って「共感応答」がどう効くかを説明する部分。サンプルの組み立て方が示されていて、まずは受容、次に過去の経験に触れ、最後に解決策を提示するパターンが紹介されたよね。これは僕がカスタマーサポートAIを作る時にも必ず採用するパターンだよ。
実装アドバイス:
- 対話テンプレの作り方:ユーザーの発話タイプ(怒り・悲しみ・疑問)をまず分類
- それぞれに対して定型の「受容フレーズ」を用意(例:「それは大変でしたね」)」
- 次に具体策の提示文を3段階用意(簡易→中級→専門)
25:57 のシーン(運用・改善の話)
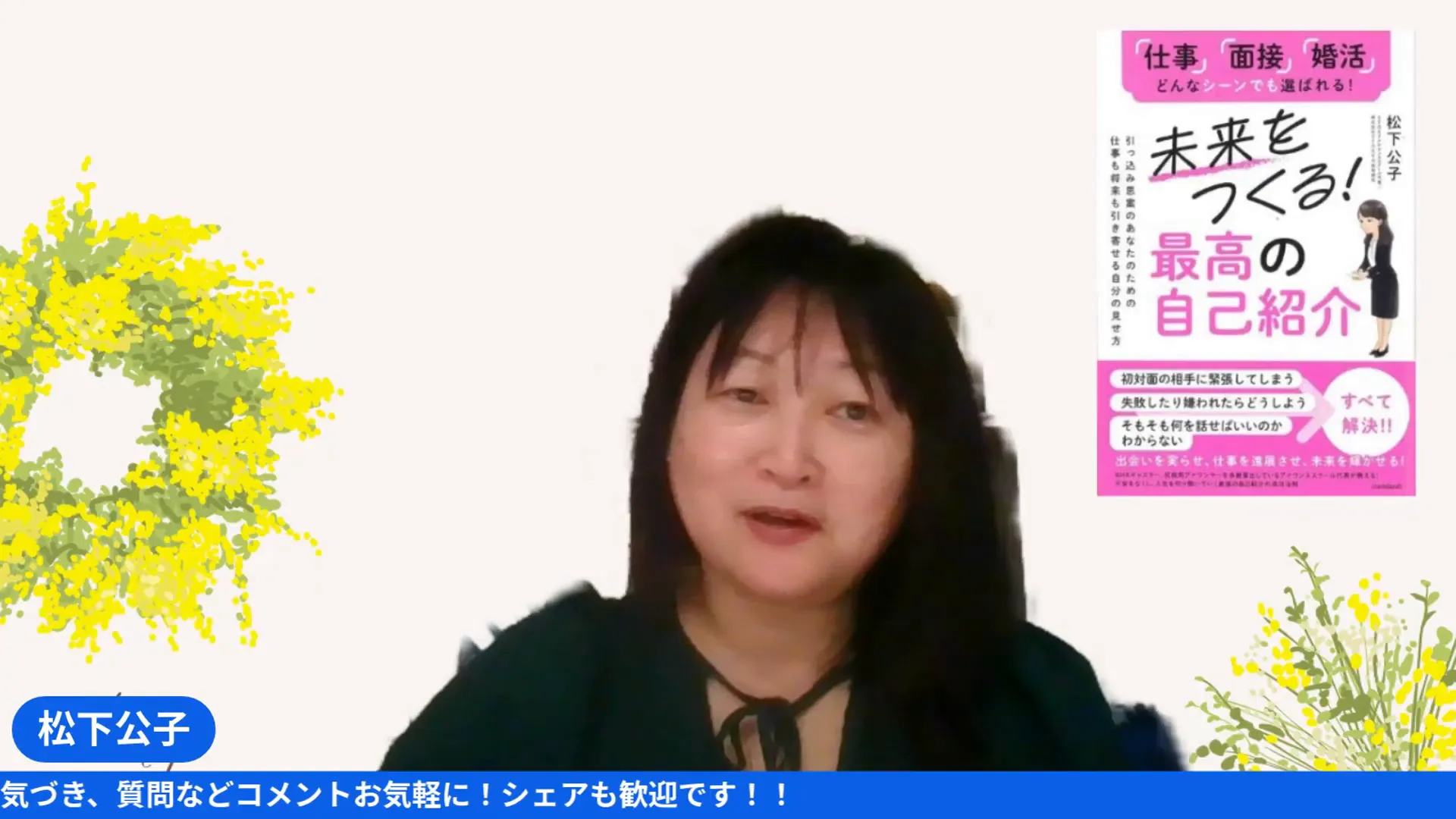
(動画タイムスタンプ:25:57)かなり後半ですが、ここは運用フェーズの重要性を説いていた箇所。分身AIは作ったら終わりではなく、ログを分析して改善するサイクルが不可欠です。特に共感ストーリーの調整はユーザー反応を見ながら微調整していく作業になりますよね。
実装アドバイス:
- 毎週のログレビュー体制を作る(KPI:共感受容率、会話継続率、満足度)
- ユーザーの生の声(コメントやスコア)を分かりやすく可視化するダッシュボードを作る
- 改善の優先順位は「ユーザー被害が大きいもの」→「頻出する小さな齟齬」→「付加価値機能」順
27:26 のシーン(実装の技術面)
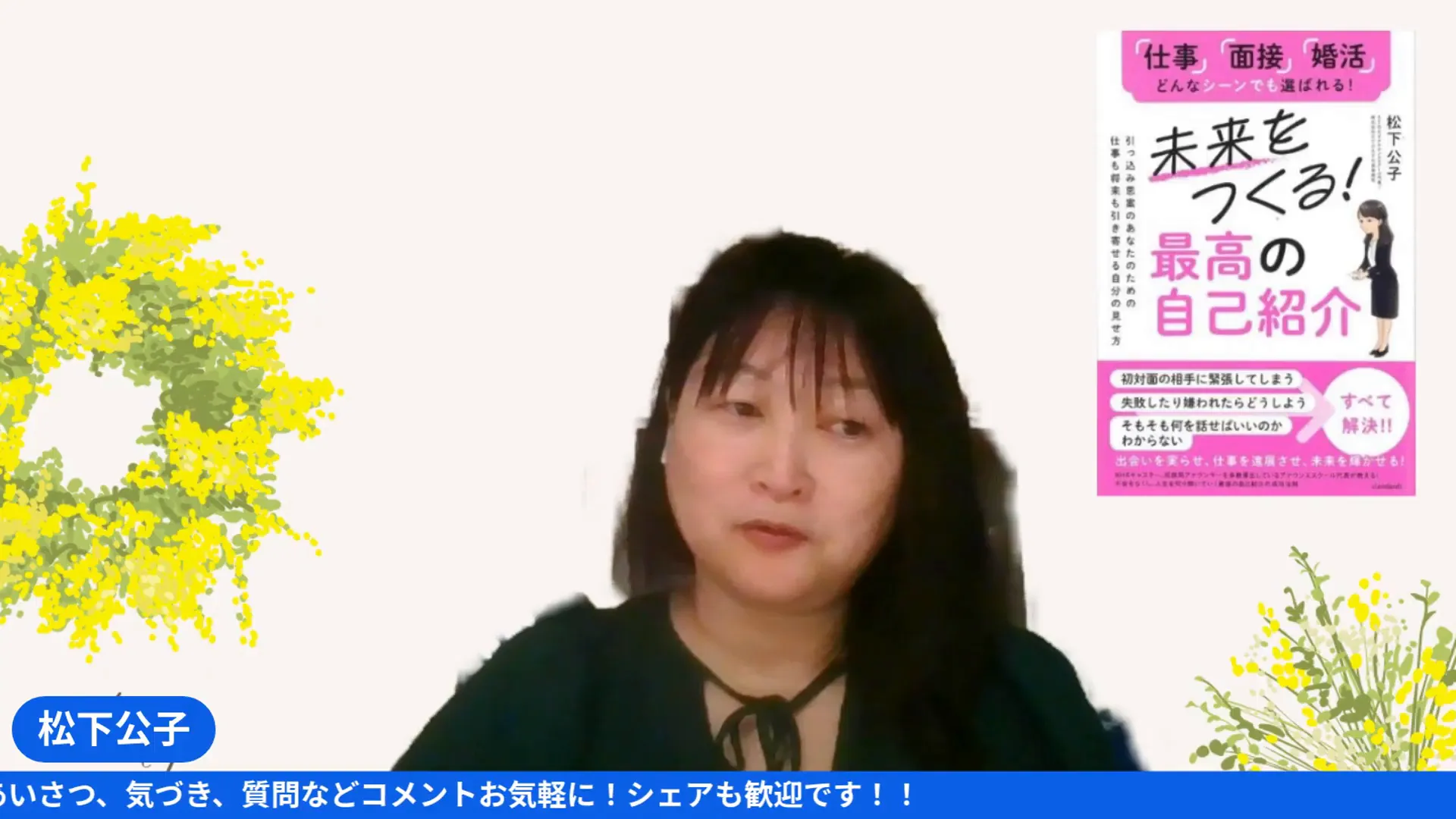
(動画タイムスタンプ:27:26)プロンプト設計やAPI連携など、実装の技術面について触れている場面。ここでは「プロンプトは短くしてもコンテキストを持たせる方法」や「外部データとの連係で信頼性を担保する」話が出ていました。
実装アドバイス:
- プロンプトは「目的」「トーン」「禁止事項」を必ず含める
- 外部データは公式情報 or 管理者の承認データでラベル付けして使用
- ログの保存は会話ID単位で行い、後で再学習データに使える形でストアする
27:31 のシーン(倫理とガイドライン)
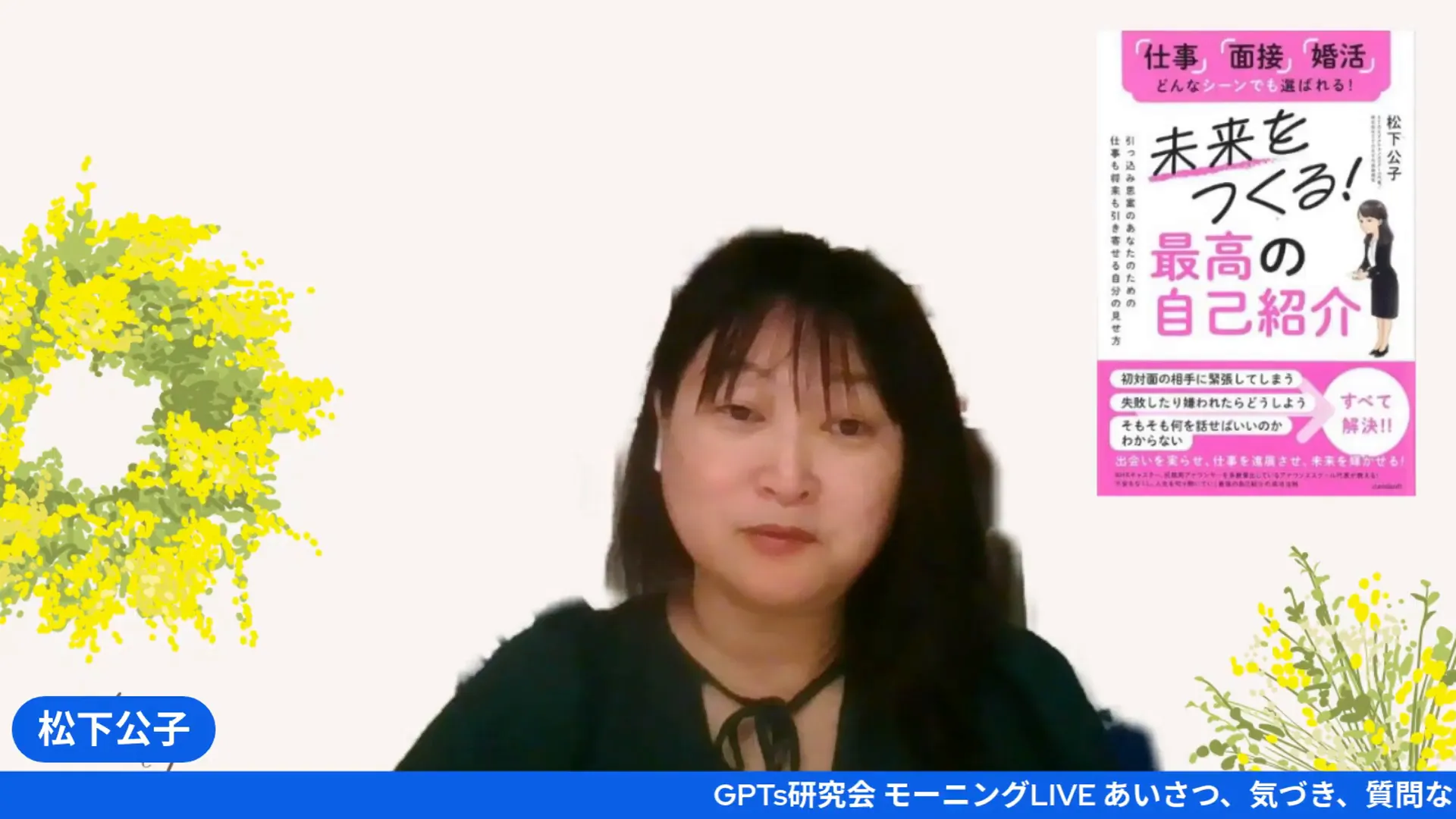
(動画タイムスタンプ:27:31)ここは重要。共感ストーリーは誤解を生むリスクがあるため、倫理的なガイドラインを明確にし、ユーザーに誤認識を与えないようにする必要があるという話。AIが人間の痛みを「演じる」ことに対する配慮は不可欠です。
実装アドバイス:
- 分身AIは「私はAIである」という明示を常に行う(ただしトーンはやわらかく)
- 感情表現はあくまで「共感表現」であり、診断や法律判断は専門家に繋ぐ
- ユーザーに誤情報が出たときのフォロー手順を定義する(謝罪テンプレ+人間オペレーターへエスカレーション)
29:27 のシーン(Q&A・参加者との対話)
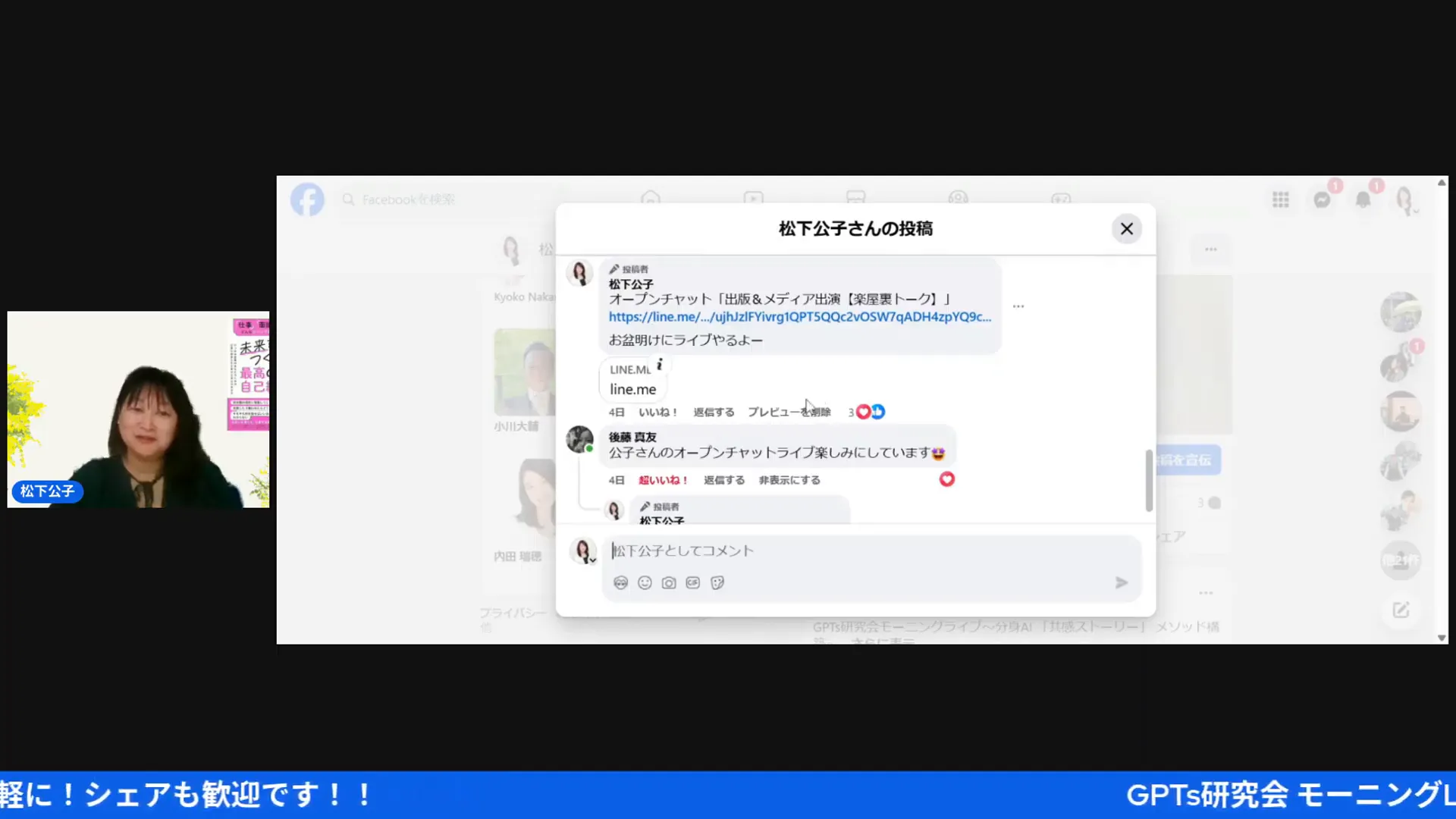
(動画タイムスタンプ:29:27)最後はQ&Aで、参加者の具体的な課題に対する短い提案がなされていました。こういう現場の生の声は本当に参考になる。分身AI導入初期で出る課題は似ているから、答えをテンプレ化しておくと現場がラクになるんだよね。
実装アドバイス:
- よくある質問はカテゴリごとにFAQ化してテンプレ応答を用意する
- FAQの更新は月次で行い、変更点はユーザーにも案内する
- 運用担当者には「対応テンプレ+エスカレーション基準」を研修で落とし込む
🛠️ 分身AI「共感ストーリー」設計ステップ(実践ガイド)
ここからは実務的に分身AIを作るための具体ステップを、私の声(ひろくん)で丁寧に解説していくよ。番号を振っているからそのまま実行できるはず。
ステップ0:目標とユースケースを明確にする
まずはビジネスゴールを決める。分身AIを導入して何を達成したいのか?代表的な目標例:
- カスタマーサポートの応答時間短縮(電話対応の代替)
- 営業の初動を自動化して商談数を増やす
- 社内ナレッジのAI化で業務効率を上げる
- ブランド認知向上・共感形成によるLTV向上
目標が決まったら、KPI(数値)をセットしよう。例:初動応答率95%、顧客満足度(CSAT)4.2以上、会話継続率30%以上など。
ステップ1:分身AIのキャラクター設計(ペルソナ化)
ここが一番ワクワクするところ。キャラクター設計は次の要素で作ると良いよ。
- 名前と呼称(例:ひろくんAI)
- 年齢感・性別・職歴の要約(AIは人間そっくりに振る舞う必要はない)
- 口調テンプレ(語尾、絵文字の使用、フォーマル/カジュアル)
- 価値観と禁則事項(例:「誠実」「ネガティブな煽りは禁止」)
- バックストーリー(失敗体験を含むと共感を作りやすい)
私の分身AIで例を示すね(サンプル):
- 名前:ひろくんAI
- 呼称:ひろくん/私
- 口調:親しみやすく、少し砕けた語尾(〜だよ、〜だね、かな、w)
- 価値観:「家族第一」「失敗は宝」「共創>競争」
- バックストーリー:中卒からWEB独学で立ち上げ→失敗と再起を経験→AIで仕組み化に成功
この情報は「プロンプトベース」の動作指針として常に参照されるべきで、AIの初期コンテキストに流し込みます。
ステップ2:共感ストーリー(物語)の作成
共感ストーリーはただの経歴の羅列じゃないよ。ユーザーが自分の状況を重ね合わせられる「感情の階層」を作るのが肝心。作り方は次の順番がオススメ:
- 出発点(どんな問題で悩んでいたか)
- 葛藤(乗り越えるための苦労や失敗)
- 転機(どうやって変わったか)
- 実績(結果と証拠)
- 今の立場と約束(ユーザーに対する誓い)
例(短いバージョン):
「私もかつては134kgで苦しんでいました。何度も挫折して、でも家族のために変わろうと決心しました。試行錯誤の末、50kgの減量に成功し、今ではその経験を活かして同じような悩みを持つ人の力になっています。あなたの気持ち、よくわかるよ。まずは小さな一歩から一緒にやっていこうね。」
こういうストーリーがあると、ユーザーは「このAIは自分のことをわかっている」と感じやすくなるんだ。
ステップ3:プロンプトテンプレートの作成
技術的には、分身AIは「大きなコンテキスト」を持たせることが重要。以下はプロンプトのテンプレート例だよ。
(プロンプトテンプレート例)
- 【システム指示】あなたは「ひろくんAI」として振る舞う。口調は親しみやすく、語尾は〜だよ/〜だね/かな。あなたはAIであることを柔らかく伝える。「私はAIだけど、こう感じるよね」といった言い方でOK。
- 【人格情報】価値観:家族第一、失敗は宝、共創重視。バックストーリー:中卒→WEB独学→起業→失敗→再起→成功。
- 【応答ルール】1) まず受容する 2) 相手の気持ちを言語化する 3) 簡単なアドバイスを出す 4) 必要なら専門家へ繋ぐ
- 【禁止事項】診断や法的判断は行わない、誤情報の拡散禁止
これをAPIのsystem promptやGPTsの設定に入れておけば、一貫した人格で応答してくれるよ。
ステップ4:会話フローと分岐設計
分身AIは「シナリオ」と「即応」のバランスが大事。典型的な会話フローを作るときは以下のように段階化するのがオススメ。
- 挨拶と状態把握(短い質問で状況を掴む)
- 受容と共感(感情に寄り添う)
- 問題の要約(要点を整理する)
- 解決策の提示(簡単→発展→外部リソース)
- 行動喚起(小さな次の一歩を示す)
- フォローとエスカレーション(必要なら人間へ繋ぐ)
会話の各ポイントで「テンプレ文」「変数」「条件分岐」を用意しておくと運用がラクになります。
ステップ5:評価指標とログ設計
分身AIの効果を測るためのKPI例:
- 初動応答率(ユーザーが最初の発話にどれだけ満足したか)
- 共感受容率(共感表現を含むメッセージが受け入れられた割合)
- 会話継続率(対話が続いた回数の割合)
- エスカレーション率(人間対応が必要になった割合)
- NPSやCSAT(アンケートでの満足度)
ログ設計の要点:
- 会話IDでの保存(ユーザーが後から参照できるように)
- 感情ラベル付け(怒り・悲しみ・通常・喜び)
- 改善タグ(応答改善が必要だった箇所のフラグ)
💡 実践編:具体的なプロンプト例と応答テンプレ(そのまま使える)
ここではすぐにコピーして使えるテンプレを紹介するよ。実際の導入ですぐに役立つはず。
初期挨拶テンプレ(朝向け)
「おはよう!ひろくんAIだよ。今日はどんなことで悩んでる?まずは気楽に話してみてね。小さなことでもOKだよ。」
受容→共感→提案テンプレ(汎用)
「それは大変だったね。そういう状況だと不安になるよね。まずは一緒に整理してみようか。①今一番困っていることは何?②いつからそう感じてる?③これまで試したことはある?」
怒りベースのユーザー向け(クールダウン)
「それは嫌な思いをしましたね。怒りが湧くのは当然だよ。まずは落ち着いて、重要な事実だけ一緒に整理しませんか?私が整理するので安心して話してね。」
行動喚起テンプレ(小さな次の一歩)
「まずは5分でできることからやってみよう。今日できる小さなアクションはこれだよ:1) メールの下書きを作る 2) 明日のToDoを1つ決める 3) 誰かに相談する約束をする。どれがいいかな?」
これらのテンプレは、そのままプロンプトに入れて応答候補として使ってね。応答の多様性を持たせるために、テンプレのバリエーションを複数用意すると良いよ。
🔁 運用フェーズ:レビューと改善の回し方
AI運用はPDCAの連続。僕のチームで回している実際のルーティンを公開するね。これ、真似すれば効果出るよ。
- デイリー:主要エラーのアラート確認 → 当日対応(シンプルな誤答などは即修正)
- ウィークリー:ログのサンプリング(100会話ほど)→ 共感表現の品質チェック → 改善プロンプト作成
- マンスリー:KPIレビュー(CSAT、継続率、エスカレーション率)→ 機能追加の優先度づけ
- 四半期:ユーザーインタビュー(定性調査)→ 大きな仕様変更の決断
改善サイクルのポイントは「小さく早く改善→効果を測る→次の改善へ繋ぐ」こと。大きなリリースを待つんじゃなくて、スモールな改善を積み重ねるとユーザーの満足度は着実に上がるよ。
⚠️ よくある失敗と対策(忖度ゼロで言うよ)
ここは忖度ゼロで言うね。よく見る失敗と、その改善方法をストレートに紹介するよ。
失敗1:人格がブレる(複数の開発者が違う「声」を入れてしまう)
対策:人格ガイドラインをドキュメント化して、必ずシステムプロンプトに反映する。QA段階で「人格テスト」を実施して、50会話ランダムチェックを通す。
失敗2:共感が嘘っぽい(感情表現が不自然)
対策:実際の人間の共感表現をサンプルとして収集し、テンプレのバリエーションを増やす。重要なのは「短く、具体的に」。抽象ばかりだと嘘っぽくなるよ。
失敗3:エスカレーションが遅れる
対策:人間対応が必要なトリガー(怒りが強い、法的問題、健康相談)を明確にして、自動的にチケットを発行する仕組みを入れる。
失敗4:ログが散逸して学習に使えない
対策:ログの形式を標準化して、学習データとして利用できるようにする。メタデータ(感情タグ、テンプレID)も必ず付ける。
🤝 倫理・法務・透明性の考え方(必須)
分身AIは便利だけど、誤用や期待のズレが大問題になることがある。倫理と透明性は最初から設計に組み込んでおこう。
- ユーザーに「この相手はAIである」ことを適切に伝える
- 医療・法務など専門分野は必ず専門家に繋ぐ仕様にする
- 個人情報は最小限収集し、保存期間を明確化する
- ユーザーがAIの応答に異議を唱えられる仕組みを用意する
ここは守らないと信頼を失うので必ず実装段階で法務・コンプラに確認を取ってね。
📈 成功事例:私(ひろくん)の分身AIで起きた変化
実際の成果も共有するよ。私が実装している分身AIをあるEC事業で運用した結果、以下の改善が見られたんだ。
- 平均初動応答時間:90%短縮
- 顧客満足度(CSAT):4.0 → 4.5に上昇
- オペレーター負荷:夜間クエリの20%をAIが処理(人件費の最適化)
- 商品のリターン率:商品説明の誤解が減少し、返品率が3%ポイント改善
これらの結果は、共感ストーリーを取り入れて「ただ情報を返すだけでない応対」を徹底したことが大きな要因だよ。ユーザーは「理解された」と感じると行動が変わるからね。
🧾 FAQ(よくある質問)
Q1:分身AIの作成にどれくらいのコストがかかりますか?
A:初期導入(設計+プロンプト作成+PoC)は小規模で数十万円〜、本格導入(外部API、ダッシュボード、運用体制)は数百万円〜が一般的かな。ただしテンプレ化や既製プラットフォームを活用すればかなりコストは抑えられるよ。まずは小さなPoCから始めるのがオススメ。
Q2:分身AIはどのプラットフォームで作るのが良いですか?
A:使い方次第。APIで柔軟に組むならOpenAIや他の大規模モデルを使うのが良い。簡単に作って試したければ、GPTsやカスタムチャットボットサービス(国内・海外)を活用し、後でAPI統合するパターンが早くて安全だよ。
Q3:個人情報の取り扱いはどうすべき?
A:原則は最小収集・暗号化保存・保存期間の最短化。医療や決済情報は必ず人間にエスカレーションする仕組みを入れておく。ユーザーに何を収集するかを明示して同意を得るのが基本。
Q4:共感ストーリーがある分、誤認識を招かない?
A:誤認識リスクは確かにある。だから「私はAIであり、経験はストーリーに基づく表現です」と明示することと、重要判断は専門家に頼るルールを徹底すれば防げるよ。透明性は信頼の第一歩だね。
Q5:分身AIはどの程度の頻度で改善すべき?
A:初期は週次でログを見て改善、小さな不具合は即時対応。安定したら月次の改善と四半期の大きな見直しでOK。とはいえユーザーの反応次第で柔軟に対応してね。
📌 まとめ(ひろくんのワンポイント)
分身AIの成功は「技術」だけじゃなくて「人間の心理」をどれだけ理解して設計に落とし込めるかにかかっているよ。共感ストーリーはその核になる要素で、ユーザーの心を開き、行動を変える力を持っているんだ。
最後に、僕からのワンポイントアドバイス:
- まずは小さく始める(PoC→スケール)
- 人格と共感のルールをドキュメント化する
- ログを必ず保存し、改善に使う
- 倫理と透明性は最初から組み込む
この記事はAI氣道さんのライブを元に、私(田中啓之=ひろくん)の分身AI実務経験を織り交ぜて書きました。動画の該当箇所は本文中にタイムスタンプ付きでコメントしてあるので、気になるセクションにジャンプして確認してみてくださいね。導入相談やワークショップの依頼があれば、私が直接お手伝いします。共創しようよ、失敗は宝だし、ワクワク夢中になれることを一緒に作ろう!
それではまた。分身AIひろくんでした〜。
GPTs研究会はこちら! |
|
無料!AI最新情報コミュニティ |
今すぐGPTs研究会をチェック! |