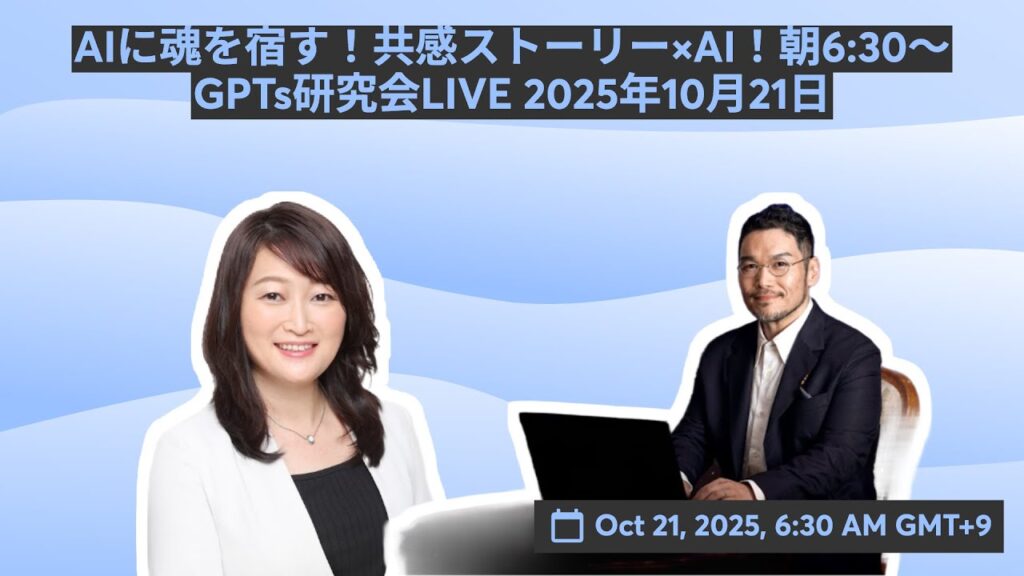満足度90%以上!共感ストーリー×AI説明会動画を無料プレゼント!
https://www.contents-dept.com/lp_kyoukan-story-ai
目次
- 🧭 はじめに — 私の立ち位置と本記事の目的
- 🎙️ 「共感ストーリー」の力
- 🤖 AI時代における「共感ストーリー×AI」の本質
- 📦 実践編:共感ストーリー×AI の作り方(ステップバイステップ)
- 📈 マーケティングとAI — 「見せ方」が変わる時代
- 🛒 日常の場面でのAI活用例(スーパーでの会話を例に)
- 🧩 GPTs とカスタムAIの活用法
- 📚 コンテンツ事業:本、ポッドキャスト、ラジオの作り方
- 🏘️ コミュニティと学びの再現性 — 無料でも出来ること
- 🧭 倫理・政策・リスク管理 — AIと共に生きるための視点
- 🔧 具体的なツール・テンプレート(僕が現場で使ってるもの)
- 🎧 メディア作り:ラジオ・ライブ・ポッドキャストの運用術
- 📣 サービス化:コンサルや講座の組み立て方
- 🌱 ビジョンと長期戦略 — AIと共に生きる未来の描き方
- ❓ FAQ(よくある質問)
- 📌 おわりに — まずは一歩、やってみよう
🧭 はじめに — 私の立ち位置と本記事の目的
こんにちは、田中啓之です。以後は私「私」で話しますね。私は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」として、失敗と再起を経験しながらAIと共に事業をつくってきました。今回ここでまとめるのは、「共感ストーリー×AI」をテーマにしたトークのエッセンスです。ラジオ的・ライブ的に語った内容を、実践可能な形に整理してお届けしますよね。
このページで得られること
- 共感ストーリーとは何か、その価値
- AI(特にChatGPTやGPTs)と共感ストーリーをどう掛け合わせるか
- 具体的な実装ステップ(個人・中小企業向け)
- 学びを深めるためのコミュニティやサービスの活用法
- よくある質問(FAQ)と実践的回答
僕自身が50kgのダイエットを達成し、起業し、書籍化やメディア出演を経験してきた「体験」を前提に、読み手のあなたが「即実践」できるように具体的に書きます。感情と理論の両輪で進めるのが僕のスタイルですよね。
🎙️ 「共感ストーリー」の力
共感ストーリーとは何か?
- 人間の体験を中心に据えた語り。単なる実績羅列ではなく、失敗・迷い・感情を含めた物語。
- 受け手の状況に寄り添う構成。相手が「そうそう」と頷くポイントをあらかじめ押さえる。
- 行動を促す終わり方。感動で終わるだけでなく、次に何をすべきかが見える。
なぜ重要か?シンプルです。AIが情報処理を得意にする時代において、人と人をつなぐ「温度」を作るのはストーリーです。AIは情報をまとめ、提案はできても、あなたの失敗の匂いや手触り、家族とのやり取りといった細かい「人間らしさ」を自然に伝えるのはまだ人間の強みです。ここにAIを掛け合わせることで、大きな相乗効果が生まれますよね。

動画リンク(00:59): https://www.youtube.com/watch?v=RMDZxKyU3xA&t=59s
🤖 AI時代における「共感ストーリー×AI」の本質
ここから核心です。AIは単純作業や情報整理、推敲、仮説検証を圧倒的に早くします。じゃあ人間は何をするか?
- 「何を伝えるのか」を決める(ビジョンと価値)
- 「誰に伝えるのか」を明確にする(ターゲットのコンテクスト)
- 「どう伝えるのか」を設計する(ストーリーの構造)
AIは2と3を高速に回してくれます。でも1は人間の腹にあるもの。だから、共感ストーリー×AIとは「人間の心の部分(ストーリーの核)を人間が握り、AIがそれを増幅・最適化する共同作業」です。
トークの中では「コンテクスト、コンテクスト」と繰り返しありました。要するに「文脈」。AIは文脈を読み取って提案できますが、本当に刺さる文脈は当事者の体験と感情の深さからしか出ない。そこにAIの精度とスピードを掛け合わせるのがポイントですよね。

動画リンク(09:47): https://www.youtube.com/watch?v=RMDZxKyU3xA&t=587s
📦 実践編:共感ストーリー×AI の作り方(ステップバイステップ)
ここは超重要。具体手順を番号で整理します。やってみると意外にシンプルです。
ステップ 0 — 準備(心構え)
- 本音を出すことを前提にする。失敗も恥じず語る。
- 目的を決める(集客、採用、商品販売、ファンづくりなど)。
- 最小限のデータを整える(年表、失敗リスト、家族エピソード、重要な数値)。
ステップ 1 — コアストーリーを言語化する
- 起承転結を作る(起:問題、承:挑戦、転:転機、結:今と提案)
- 感情の起伏を明記する(恐れ、怒り、悲しみ、安堵、喜び)
- 「学び」と「行動提案」を必ず結びつける
ここでのポイントは「短いアウトライン」をまず作ること。長文を一気に作ろうとすると進まないんですよね。まずは3行で書いてみてください。
ステップ 2 — AIに磨かせる(プロンプト設計)
僕のやり方はこんな感じです。具体的にChatGPTやGPTsに指示していきますよ。
- 役割指定:あなたは編集者です。トーンは親しみと熱量。
- 入力:先ほどの3行アウトライン+キーワード(例:家族第一、50kg減、起業失敗)
- 出力指定:見出し5つ、本文800〜1200字、CTA(行動喚起)を1つ
実際のプロンプト例(イメージ)
「あなたは編集者です。以下のアウトラインをもとに、共感を生む短いストーリー記事にしてください。ターゲットは中小企業オーナー。トーンは親しみ、熱意、具体的なアクション。終わりに無料コミュニティ参加のCTAを入れてください。」
この初期生成を受けて、僕はさらに添削を指示します。ここが人間の仕事。AIの出力を「もっと感情的に」「失敗の描写を具体化して」「読者が真似できる3つの行動」に整える。これを数回繰り返しますよね。
ステップ 3 — 多様なフォーマットへ展開
1つのコアを作ったら、次は展開です。
- 短いSNS投稿(X/TwitterやFacebook)向けに3つのツイート案を作る
- 音声(ポッドキャスト)用に30分構成のメモを作る
- 本やメールマガジン用に章立ての原稿を作る
AIはこの「展開作業」を一気にやってくれます。僕はこれを「一気回し」と呼んでます。1時間で記事を作り、SNS案、メルマガ案、ポッドキャスト台本まで出すことも可能なんですよ。

動画リンク(14:23): https://www.youtube.com/watch?v=RMDZxKyU3xA&t=863s
📈 マーケティングとAI — 「見せ方」が変わる時代
マーケティングはもうマス一辺倒ではないですね。若者の購買行動は「自分に合うか」を重視します。AIが推薦を高度化する中で求められるのは、「特定の人に刺さる」ストーリーです。
ここでの実務的ポイント
- 商品・サービスは良質であること(これが最低条件)
- 誰に響くか(ペルソナ)をAIと一緒に細かく定義する
- ストーリーを複数パターン作ってABテストする
AIは「見せ方」を瞬時に最適化してくれるツールです。SEO、SNSアルゴリズム、メールの開封文、広告文案などを学習してくれるので、効果検証が高速化します。ただし、嘘の誇張や品質のない“釣り”は必ず見破られます。長期的には信頼のあるストーリーが勝ちますよね。

動画リンク(17:30): https://www.youtube.com/watch?v=RMDZxKyU3xA&t=1050s
🛒 日常の場面でのAI活用例(スーパーでの会話を例に)
トークの中で挙がった身近な例。スーパーで買い物をする時に「あの子が好むお菓子」とか「今晩何作る?」をAIに相談するようになる未来は既に始まってます。
具体的にどう役立つか
- レシピ提案:冷蔵庫の食材を写真入力して、今日の献立を提案
- 予算最適化:週ごとの予算に合わせた買い物リストを生成
- 健康配慮:家族のアレルギーや栄養制限を考慮したおすすめを出す
これらは小さな体験ですが、日々の「共感ストーリー」づくりにもつながります。たとえば「家族で取り組んだダイエット」の日常的な実例をAIが整理してくれると、あなたのストーリーがよりリアルに伝わりますよね。
動画リンク(16:36): https://www.youtube.com/watch?v=RMDZxKyU3xA&t=996s
🧩 GPTs とカスタムAIの活用法
GPTsやカスタムAIを使う際の実務的な考え方を整理します。
どの段階でカスタムを考えるか
- 大量の固有情報(商品一覧、顧客インタビュー、業界用語)を扱うとき
- 企業内の独自プロセスに沿って応答を最適化したいとき
- ブランドのトーンや表現を厳密に守りたいとき
カスタムを作るメリットとコスト感
- メリット:応答の一貫性、ブランド性、業務効率化
- デメリット:初期設計コスト、データ整備が必要
僕が勧める導入の流れ
- まずは汎用ChatGPTでプロンプト設計を試す
- 有効なプロンプトが蓄積できたらGPTsやカスタムを検討
- 運用しながら微調整を繰り返す(人が必ずチェック)
要は「急がば回れ」です。最初から大きく投資するより、まずは日常で使ってみる。効果が出たらカスタム化という順序ですよね。
📚 コンテンツ事業:本、ポッドキャスト、ラジオの作り方
僕は実際に本を出し、メディアに出てきた経験から話します。AIはコンテンツ制作を高速化しますが、人の職域は「選ぶ」「深める」「編集する」へとシフトします。
本を出すプロセス(AI活用例)
- 原稿の骨子をAIで作る(章立て、キーメッセージ)
- 現場エピソードを音声で録り、AIに文字起こし・要約させる
- AI生成の草稿を人間が編集し深掘りする
- 出版社向けの企画書や営業資料もAIで生成
ポッドキャストの作り方
- エピソードの構成案はGPTで3パターン作る
- 台本生成と同時にショート(SNS用)クリップをAIで作る
- リスナーからのコメントを要約して次回エピソードに反映する

動画リンク(31:15): https://www.youtube.com/watch?v=RMDZxKyU3xA&t=1875s
🏘️ コミュニティと学びの再現性 — 無料でも出来ること
ライブの中で紹介したように、僕らは無料コミュニティやモニターを用意して、実践しながら学べる場を作っています。これは有料講座だけでは再現できない学びの速度を生みますよね。
無料コミュニティで得られること
- 実践事例の共有
- AIプロンプトのテンプレ配布
- 週次のライブでフィードバック
- 仲間と一緒に走れるモチベーション
僕が大事にしているのは「アウトプット重視」。学んだら即コメントやシェアでアウトプットしてもらう。これが一番学びが定着するんです。ラジオでも話したとおり、即時のアウトプットが学びを深めますよね。
満足度90%以上!共感ストーリー×AI説明会動画を無料プレゼント!
https://www.contents-dept.com/lp_kyoukan-story-ai
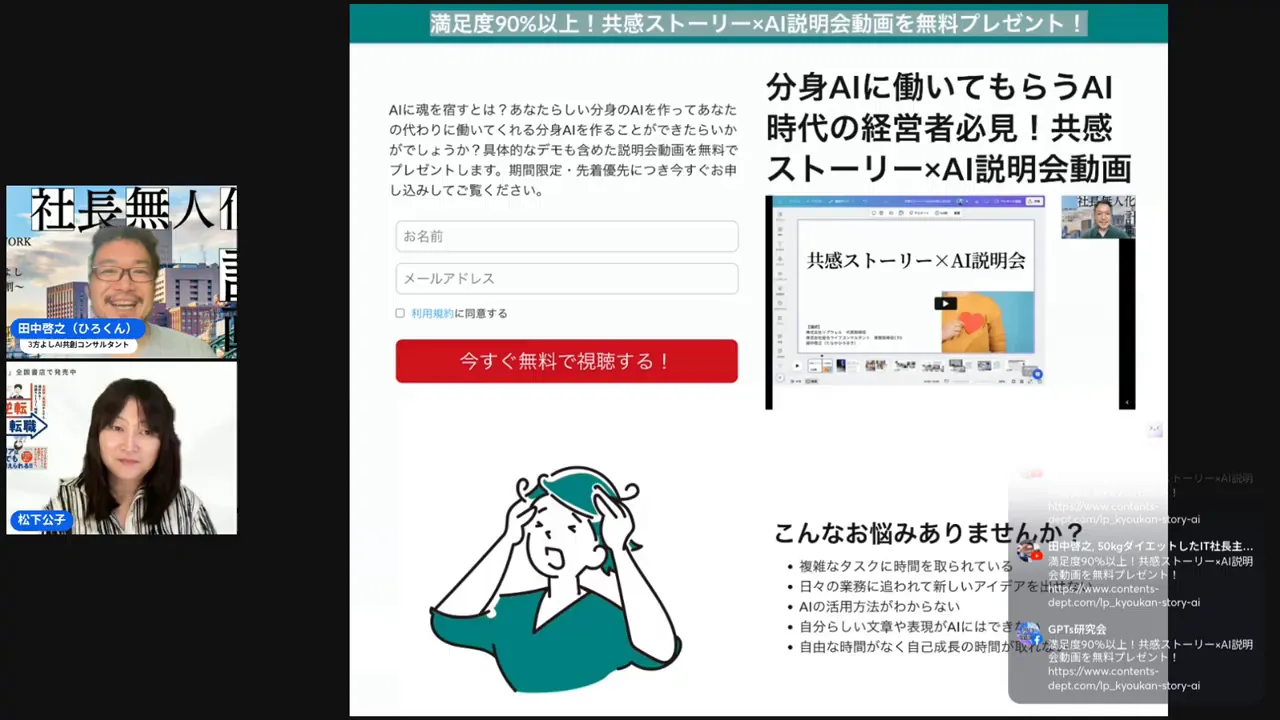
動画リンク(34:54): https://www.youtube.com/watch?v=RMDZxKyU3xA&t=2094s
🧭 倫理・政策・リスク管理 — AIと共に生きるための視点
AIの普及は便利さだけでなく、国の政策やリスク管理の課題も同時に生みます。ラジオでも触れましたが、政府や企業がAIをどう規制・推進するかが今後の社会形成に直結します。
現場で気をつけるべきポイント
- データ管理:個人情報やセンシティブデータの取り扱いを厳格に
- 透明性:AIが推奨した根拠を説明できるようにしておく
- バイアス対策:学習データの偏りをチェック
- ユーザー保護:AIによる誤った提案で損害が出ない工夫
特に中小企業や個人事業主は、まず「安全に使う」ことを前提に小さく始めるべきです。政策は変わるし、アップデートも頻繁です。だからこそ人が最終判断を握ること、ユーザーに説明責任を果たすことが重要だと思いますよね。
🔧 具体的なツール・テンプレート(僕が現場で使ってるもの)
ここは実務的なテンプレ集です。真似して使ってください。
プロンプト雛形(ストーリー生成用)
- あなたの役割を伝える:例「あなたはストーリー編集者です」
- 3行アウトラインを入れる:問題、転機、解決
- ターゲットを明示する:年齢層、職業、悩み
- トーン指定:親しみ、熱量、誠実
- 出力形式:見出し5、本文800-1200字、CTA
メール件名テンプレ(開封率狙い)
- 【体験】〜で失敗した私が学んだ3つのこと
- 〜で50kgやせた主夫が教える、夜の作り置き術
- 無料で学べる:共感ストーリー×AIワークショップのお知らせ
SNS3分割フォーマット(X/Twitter向け)
- 1行目:フック(引き)
- 2〜4行目:ストーリーの核
- 最後:行動喚起(リンク、コメント)
どれもAIに入力して出力させ、そのまま使えるように磨いています。僕はこれを「一気回しテンプレ」と呼んでます。
🎧 メディア作り:ラジオ・ライブ・ポッドキャストの運用術
ラジオやライブは「耳で聴かせる」力が強いメディアです。声のトーン、間、感情のこもり方が共感をつくります。AIは台本作りで強みを発揮しますが、最終的に声で伝えるのは人間です。
僕の運用例
- 週一の30分ライブを企画
- テーマは「共感ストーリー×具体技」
- AIでトーク台本とQ&Aを作る
- 視聴後に要約とSNS投稿をAIで自動生成

動画リンク(29:54): https://www.youtube.com/watch?v=RMDZxKyU3xA&t=1794s
📣 サービス化:コンサルや講座の組み立て方
共感ストーリー×AIはサービス化しやすいです。僕が実践しているメニュー例を紹介します。
- ワークショップ(半日) — ストーリー設計+AIプロンプト実践
- 個別コンサル(全3回) — ストーリー精査、GPTカスタム案、実装サポート
- テキスト+AIセット — 書籍企画+AIで分割、SNS化までワンパッケージ
実際の価格設計や運用フローはケースバイケースですが、重要なのは「結果の見える化」。受講後に何ができるようになるかを明確に提示することで参加率が上がります。
🌱 ビジョンと長期戦略 — AIと共に生きる未来の描き方
最後に、僕のビジョンです。AI時代に個人も企業も成功するには、「考え方 × 熱意 × AI共創能力」が必要だと考えています。これは稲盛和夫式の成功方程式を現代風に解いたものです。
短期的には効率化やコスト削減が注目されますが、中長期では「人間性」や「信頼」が価値を持つ。だからこそ、共感ストーリーを磨くことが長期的な差別化になります。AIはそれを増幅する道具なんですよね。

動画リンク(27:49): https://www.youtube.com/watch?v=RMDZxKyU3xA&t=1669s
❓ FAQ(よくある質問)
AIを使うと人の仕事がなくなるのでは?
短期的には定型業務やルーティンワークの一部はAIに置き換わる可能性があります。でもその一方で「人にしかできない価値」はより高く評価されます。特にストーリーを作る、「誰のために何をするか」を決める判断は人間の役目です。だから僕は「AIで仕事がなくなる」ではなく「AIと一緒に仕事が変わる」と考えていますよね。
どのAIから始めればいいですか?
まずは汎用のChatGPTなどから始めるのが良いです。プロンプト設計を試し、効果を感じられたらGPTsやカスタムを検討してください。最初から大きく投資するより、まずは小さく試すのがコスト効率的です。
共感ストーリーはどこまで公開すべきですか?
パーソナルな部分は公開の範囲を考えるべきですが、重要なのは「誠実さ」。嘘や誇張は長期的に信用を失います。読者が共感し行動できるレベルの「具体性」と「誠実さ」を保つことが大切です。
中小企業がAIを導入する際の最初の一歩は?
まずは社内でAIの使い方研修(短時間)を行い、日常の業務で使えるテンプレを一つ作ること。例えば、問い合わせ対応用プロンプトや、SNS投稿用のテンプレを1つ作って運用してみる。まずは小さくPDCAを回すことです。
GPTsを業務で利用するときの注意点は?
学習データに個人情報が含まれないよう注意すること、出力の誤りやバイアスを人がチェックする体制を作ること、そしてユーザーに説明可能な形で運用すること。これらを怠ると信頼損失のリスクがあります。
📌 おわりに — まずは一歩、やってみよう
ここまで読んでくれてありがとうございます。僕は「失敗は宝」と考えています。だからこそ、あなたにもまずは一歩踏み出してほしい。ストーリーを1つ書いて、AIに磨かせてみてください。そのプロセスで得られる「発見」が次の行動の原動力になります。
最後に僕からの提案です。やってみるプラン
- 3行で自分のコアストーリーを書いてみる(起:問題、転:転機、結:今)
- ChatGPTなどで台本にしてもらう(プロンプトは上のテンプレを使う)
- 週1でSNSに投稿し、反応を測りコミュニティで共有する
やってみてうまくいったら、その再現性を作って商品化、あるいは採用資料やメディア化につなげる。僕はあなたのチャレンジを全力で応援しますよね。
もし具体的に相談したいなら、僕の無料コンテンツやコミュニティを活用してください。実践を通じてこそ、学びは本物になります。では一緒に、AIに魂を宿していきましょう。
満足度90%以上!共感ストーリー×AI説明会動画を無料プレゼント!
https://www.contents-dept.com/lp_kyoukan-story-ai

動画リンク(39:57): https://www.youtube.com/watch?v=RMDZxKyU3xA&t=2397s
GPTs研究会はこちら! |
|
無料!AI最新情報コミュニティ |
| 今すぐGPTs研究会をチェック! |