おはようございます。AI氣道チャンネルのひろくんこと田中啓之です。今回のモーニングライブでは、朝の短い時間にみんなとシェアした「寝坊&配信トラブル」から派生した気づき、体調やデバイスの不調、そして僕がずっと取り組んでいる「分身AI」と「共感ストーリー」メソッドについて、ライブの内容をベースにより実践的で深掘りした形でお届けします。動画そのものはチャンネルにあるので、記事の中でタイムスタンプも付けて参照しやすくしていますよ。
目次
- 🕰️ 朝の遅刻(寝坊)から得た3つの学び
- 💻 配信とデバイス不調、そして“次元上昇”理論
- 💊 体調不良からの復帰と健康の投資
- 📚 新刊(4冊目)予告とコンテンツ作りの裏側
- 🎤 準備しない喋り方――それは弱点か武器か?
- 🤖 分身AIと「共感ストーリー」メソッドの全体像
- 🛠️ 分身AIの導入実務ガイド(ステップバイステップ)
- 📈 「共感ストーリー」応用ケース:3つのユースケース
- 🔍 SEO視点から見た「共感ストーリー」コンテンツ設計
- 📎 実践ワーク:分身AIに教える「共感ストーリー」テンプレ10選
- ❓ FAQ — よくある質問
- 📌 最後に:私のスタンスとこれからの約束
🕰️ 朝の遅刻(寝坊)から得た3つの学び
まずは、ライブの冒頭でやらかした「寝坊」の話から入りました。ライブは通常6:30から開始しているところ、この日は寝過ごしてしまい、あれよあれよという間に時間が過ぎてしまった。配信ツール(ストリームヤード)も最初はうまく繋がらず、慌てたんだけど結果的には配信できた、という流れですね。
この「寝坊」と「配信トラブル」の体験から、僕が日頃大事にしている考え方や行動原則が改めて見えてきました。ここでは学びを3つに整理しておきます。
- 柔軟性を持った設計の重要性:仕組みやスケジュールは完璧にしておくに越したことはないけど、何かが壊れたときの代替フローを用意しておく。ライブでいうと代替の配信手段、録画アップロードの準備など。
- “失敗は宝”というマインドセット:僕のモットーのひとつ「失敗はネタ」。寝坊や機材トラブルも後で振り返ればコンテンツの種になるし、同じことで悩む誰かの助けになる。
- リアルタイム協働の価値:ライブでリアクションを見ながら話すのが好きな自分にとって、準備し過ぎない“今”を話すスタイルは武器にもなる。ただし、それが弱点になる場面もあるのでバランスが大事。
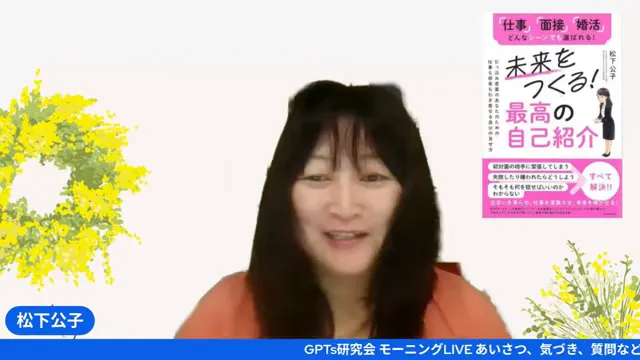
(動画タイムスタンプ参照: https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=29s)
この場面では、朝の挨拶と「今日は寝坊してしまった」という自己開示で視聴者との距離を縮めています。共感ストーリーの入り方としては理想的な例。最初に弱さを見せることで、視聴者は一気に親近感を抱きやすくなるんだよね。
💻 配信とデバイス不調、そして“次元上昇”理論
ライブ中にパソコンの動作が重くなったり、Facebookが一時的に使えなくなったりと、テクノロジートラブルが続きました。僕はこれを「次元上昇の前兆」として捉えることがあるんですよね。ちょっとスピリチュアルに聞こえるかもしれないけど、経験的に「環境の変化=道具が合わなくなる」という感覚は無視できない。
- 道具の寿命とステージの切り替え:起こる現象としては単純で、ハードウェアが古くなったりOSが不調になったり。でも心理的には「何かが変わる」サインに感じることがある。
- デバイスの波動が合わなくなる仮説:僕は「自分が次のステージに行くと旧ツールと波動が合わなくなり、ツールが壊れる」という見方をしている。これは比喩でもあって、実務的には「新しい挑戦には新しいツールが必要」という話に直結する。
- 準備と投資の再配分:壊れたら新しい機材に投資するいい機会。これをポジティブに捉えて、次の一手を早く打つ。
(動画タイムスタンプ参照: https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=195s)
デバイス慢性的に重い時は、まずはログの確認、不要プロセス停止、そして最終的にバックアップ→新調というステップが必要。これ、分身AIを動かす上でも同じです。古い学習データや運用設計を引きずると、思ったほど動いてくれないことがある。
💊 体調不良からの復帰と健康の投資
最近は僕自身も体調を崩した経験があって、その話もライブで触れました。体調を崩すときって精神的な負荷や環境の変化が重なっている場合が多い。僕はこういうときこそ、逆に「得るもの」があると考えるタイプです。
具体的には:
- 一旦休むことで視点が切り替わる
- 何が効率悪かったかを見直すキッカケになる
- 家族や仲間の大切さを再確認できる
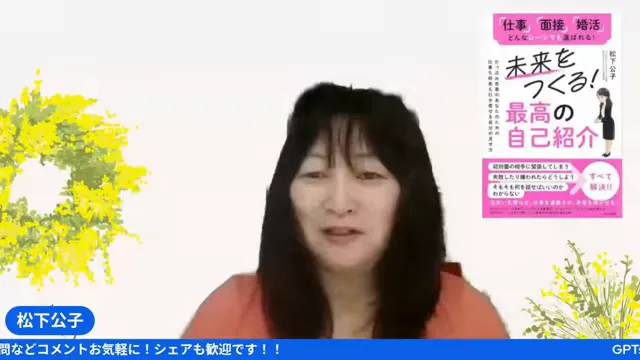
(動画タイムスタンプ参照: https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=151s)
僕の人生のバックボーンを語ると、住宅設備ECでの成功と大きな負債、そして134kgから83kgへ-50kgダイエットに成功したこと—こういった転機が今の自分を作っています。体調の不調は一見マイナスだけど、その裏には再設計のチャンスがあるって信じてるんだよね。
📚 新刊(4冊目)予告とコンテンツ作りの裏側
ライブでもお伝えした通り、来月に新刊(僕にとって4冊目)が出ます。今回はまだ細かい内容は言えないけど、表紙はできており、原稿のブラッシュアップ中。こういうときに学んだことを少しシェアします。
- 原稿は一度で完璧にしようとしない:初稿→校正→第三者レビュー→現稿チェックの流れを繰り返す。改善の余地を残すことが肝。
- 伝える順番を重要視する:共感を生む導入→問題提起→経験談→再現できるステップ→まとめ、という順序で書くと読者の行動率が上がる。
- 分身AIと共感ストーリーを活用:今回の本でも、分身AIを読者誘導やワークショップ運営にどう使うかは触れていく予定。AIで一貫したメッセージを出すときに“共感ストーリー”が役に立つ。
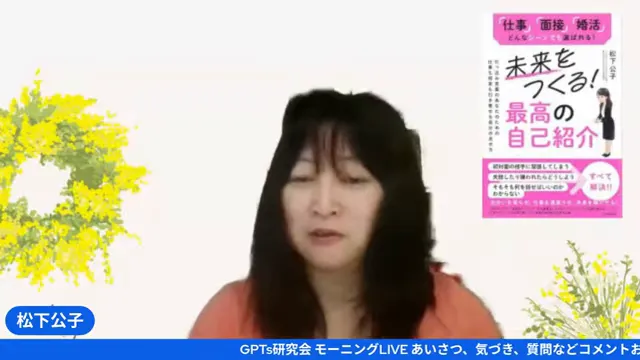
(動画タイムスタンプ参照: https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=274s)
出版は「伝える力」を磨く絶好の場。読者の行動を変えるには、ただ情報を並べるだけでなく、感情の流れ(共感→気付き→行動)を設計することが大事なんだよね。
🎤 準備しない喋り方――それは弱点か武器か?
ライブでよく言っているのが「私は準備しないで喋ることが多い」ということ。これ、外から見ると「無責任」って見えるかもしれないけれど、僕には明確な理由とメリットがあります。
まず、即興で話すことのメリット:
- 視聴者の空気を読みながらその場で最も響く話題にフォーカスできる
- その場のリアクションでコンテンツの方向性が決まるため、エンゲージメントが高くなる
- 準備をしない分、自然で等身大のトーンが伝わる
ただし欠点もある:
- 要点がわかりにくくなる危険がある
- 時間管理が甘くなる(話が長くなる)
- 一貫性を失う可能性がある
だから僕は、自分の“準備しない”という性質を理解した上で、それを“武器”に変えるための最低限の仕組みを作っています。例えば:
- テーマだけは用意(今日のライブは「寝坊」と「近況」)
- 重要な告知(新刊発売日など)はメモに残す
- ライブ後に必ずフォロー(ブログやSNSで要点整理)
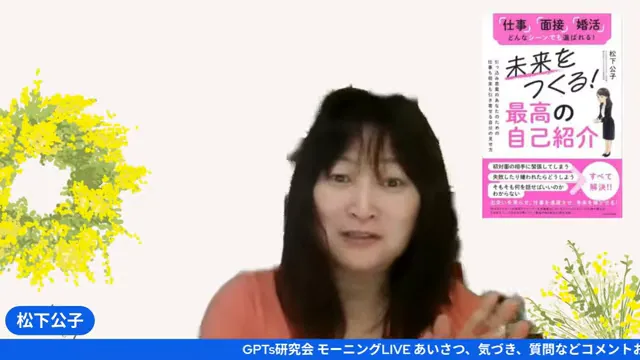
(動画タイムスタンプ参照: https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=376s)
この「準備しない」スタイル、失敗も多いけど、それを含めての僕なんだよね。応援してくれる人も「そのままのひろくん」でいてほしいって言ってくれるから、それに応える形でもあるよ。
🤖 分身AIと「共感ストーリー」メソッドの全体像
ここからがこの記事の肝。タイトルにもある「分身AI」と「共感ストーリー」メソッドを、ライブの内容と僕の経験を踏まえて実務レベルで解説します。分身AIを作って運用する際に、ただ知識を詰め込むだけでは不十分。感情や価値観、語り口まで再現して初めて“分身”になります。
僕が推奨する「共感ストーリー」メソッドの全体像は以下の通り:
- 核となる人物像(ペルソナ)を設計する
- 共感ポイント(失敗、困難、希望)を整理する
- 語り口・話し方(トーン、言い回し、擬音)を定義する
- 実践的テンプレート(導入→葛藤→解決→行動)を用意する
- AIに実装し、会話ログで検証→改善を回す
ここからは一つずつ詳しく解説するよ。
1. 核となる人物像(ペルソナ)を設計する
分身AIを作る前に、まずその「人」が誰なのかをクリアにする。僕自身の分身AIなら、以下が含まれます:
- 名前:田中啓之(ひろくん)
- 年齢:45歳(1980-05-02生)
- 出身/現住:東京都板橋区→港区芝浦
- 家族構成:妻、長男(2015年生)、長女(2023年生)、次女(2024年生)
- バックグラウンド:中卒、WEB独学、住宅設備ECでの成功と負債、-50kgダイエット経験、AI共創ビジネスで複数社CEO
- 価値観:家族第一、愛と感謝の循環、共創重視、失敗は宝
これをAIに渡すことで、会話の基本軸がぶれなくなる。ペルソナはただのプロフィールではなく「価値観の設計」でもあるんだ。
2. 共感ポイント(失敗、困難、希望)を整理する
人は感情に動かされる。共感ストーリーとは、その感情の流れを作ること。僕の場合は次のように整理しています:
- 失敗:ECでの詐欺被害や負債、体重増加(134kg時代)
- 試練:治療やダイエットの継続、家族への責任
- 回復:-50kgダイエットの成功、書籍化、メディア出演
- 希望:AI共創で“社長無人化”を実現し、埋もれた才能の支援をしたい
この構造は短いライブの導入でも使えるし、分身AIが相談対応をするときのテンプレにもなる。
3. 語り口・話し方を定義する
語り口は分身AIが人間らしく感じられるかの要。僕の話し方の特徴は:
- 一人称は「私」だが、親しみを込めて「ひろくん」と呼ばれることが多い
- 語尾のトーン:「〜だよ」「〜だね」「かな」「w」など砕けたフレーズを混ぜる
- 応援型で熱量がある:励ますときは具体例と経験を出す
- 忖度ゼロ:良い点は褒める、問題は違うと断言して改善策を出す
これをテンプレ化してAIのプロンプトに入れておくと、単なるFAQボットではなく「ひろくん」の分身が出来上がる。
4. 実践的テンプレート(導入→葛藤→解決→行動)
共感ストーリーの王道テンプレを示すと:
- 導入(自己開示):「実は先日こんなことがあって…」
- 葛藤(問題提示):「そこでこんな悩みが出た」
- 解決(経験談):「私はこうしたらうまくいった」
- 行動(読者への促し):「まずは○○をやってみよう」
ライブの冒頭の「寝坊→配信トラブル」はこのテンプレの縮小版。短時間で共感を生むのにとても有効だよ。
5. AI実装と改善ループ
AIに実装する際は、まず上記データをプロンプト化してベースモデルに流し込む。最初は下記手順で。
- ペルソナデータと語り口ガイドをプロンプトに書く
- 代表的な共感ストーリー事例を複数入力する(ライブや過去の発言)
- 対話シナリオを作成し、最初は手動でテスト
- 実運用ログを収集し、応答のズレを修正
- 定期的に再学習(新しいコンテンツや考え方を追加)
この「収集→修正→再学習」のループは分身AIを育てる上で最も重要で、怠ると人格が微妙にズレるよ。

(動画タイムスタンプ参照: https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=422s)
🛠️ 分身AIの導入実務ガイド(ステップバイステップ)
ここからは実務的な導入手順を具体化します。僕がコンサルで話している内容そのままね。分身AIを社内・コミュニティ・商品サポートに導入したいときのチェックリストだよ。
ステップ0:目的の定義
- 顧客対応の省力化か、マーケティングか、コンテンツ作成の自動化か?目的を明確化する。
- KPIを設定(応答率、満足度、リード獲得数など)。
ステップ1:ペルソナとトーンの設計
- 上で述べたペルソナ詳細を用意。
- やってはいけない表現も明記する(例:断定的な医療アドバイスをしない等)。
ステップ2:共感ストーリーライブラリを作る
- 過去のライブやブログ、書籍から共感ストーリーを10〜30本ピックアップ。
- テンプレ化してタグ付け(例:家族、健康、失敗→学び、ツール)する。
ステップ3:スクリプトとプロンプト設計
- 導入、質問の受け方、否定的反応への対応テンプレを作成。
- FAQは最初に優先度をつけ、AIの応答に必須フレーズを盛り込む。
ステップ4:実装とテスト
- まずはベータユーザーを少数選び、実運用ログを集める。
- ログから誤りのルールを洗い出し、プロンプトを調整。
ステップ5:運用と改良
- 月次でログレビューと改善を行う。
- 大きな方向性変更は四半期ごとに実施(外部環境が変われば人格設計も見直す)。
これらをやることで、単なるチャットボットではなく「あなたの分身」として機能するAIができるよ。

(動画タイムスタンプ参照: https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=492s)
📈 「共感ストーリー」応用ケース:3つのユースケース
ここでは実際に分身AIと共感ストーリーを組み合わせた活用事例を3つ紹介します。どれも僕が関わった現場で効果を出した実践例だよ。
ユースケース1:商品購入のコンバージョン向上(EC)
背景:ECサイトで離脱率が高い。原因は商品ページの一方向的な情報提供。
実装:
- 商品ページに分身AIを差し込み、訪問者の疑問や不安を聞き出す(例:「取り付け簡単ですか?」)
- 共感ストーリーを活用して回答(例:「私も最初は心配だったけど、家族と一緒に30分で設置できたよ」)
- 最後に行動を促す(割引クーポンやFAQへの誘導)
効果:感情的な安心が買い手の決断を促し、CVR(コンバージョン率)が改善したケースが多数。
ユースケース2:コミュニティ運営のエンゲージメント向上
背景:オンラインコミュニティ参加率が低く、会話が続かない。
実装:
- コミュニティ内で分身AIが、参加者の投稿に対して共感コメントや体験談を返すように設定。
- ストーリー性のある返信で会話が膨らみ、他メンバーの参加を促す。
効果:投稿数とリアクションが増え、運営側の負担が減りつつコミュニティの熱量が保てた。
ユースケース3:講演・ワークショップの自動化
背景:講演の数が増え、毎回同じ話をする手間がかかる。
実装:
- 分身AIに講演のイントロやQ&A対応のテンプレを覚えさせる。
- ライブ中の質疑応答はAIが一次対応し、重要な質問は人間がピックアップ。
効果:講演の質は落とさず、スケールさせられた。時間当たりの情報提供量が増加したよ。

(動画タイムスタンプ参照: https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=562s)
🔍 SEO視点から見た「共感ストーリー」コンテンツ設計
分身AIや共感ストーリーは単なるコミュニケーションツールではなく、SEO的にも強い資産になります。理由はシンプル:ユーザーが検索する「悩み」に対して、長期的に価値のある共感型コンテンツを提供できるから。
- ロングテールキーワードに強い:体験談や具体事例を含むことで、検索クエリに対する自然言語一致率が上がる。
- 滞在時間が伸びる:感情に訴えるストーリーは読了率が高く、滞在時間(SEO指標)を伸ばす。
- 再訪問の動機になる:分身AIがパーソナライズされたフォローを行うと、ユーザーが戻ってくる確率が上がる。
具体策としては:
- 記事やFAQに共感ストーリーを入れる(トップに一つ、各セクションの導入に一つ)
- 分身AIの会話ログを匿名化してFAQや記事のインプットに使う
- ストーリーコンテンツはSNSで切り取りやすいように短く分割して投稿
📎 実践ワーク:分身AIに教える「共感ストーリー」テンプレ10選
ここはそのままプロンプトに貼れるテンプレ集。分身AIに入れてすぐ使えるようにしてあります。
- 「私も最初は○○で悩んでいて…でも□□をやったら改善したよ」
- 「家族のためにやったことが、結果的に自分を救った話」
- 「失敗したときの具体的手順:1)受け止める 2)相談する 3)小さく試す」
- 「時間がない人向けの3ステップ実践法」
- 「やってはいけないNG行動と代替案」
- 「私が試したツール比較(短所・長所)」
- 「失敗から得た数字的効果の事例(Before/After)」
- 「よくある質問に対するQ&A+体験談」
- 「安心を与える言葉(例:大丈夫だよ、まずは○○からでOK)」
- 「最後に行動を促す一文(例:まずは今日○分やってみよう)」
❓ FAQ — よくある質問
Q1: 分身AIを作るのに専門知識は必要ですか?
A1: 最初はプラットフォームを使えば専門知識がなくても作れます。ただし「人格設計」や「運用ルール」は必須で、ここは専門家の支援を入れると早いですね。私はコンサルでそういう支援もしていますよ。
Q2: 共感ストーリーが薄くなってしまうAIの応答はどう直す?
A2: 応答ログを集めて、どのポイントで感情が途切れているかを分析。具体的には「語尾」「自己開示の頻度」「ストーリーの比率」を調整します。手順としては(1)ログ分析(2)仮説立案(3)プロンプト修正(4)A/Bテストが効果的。
Q3: AIに個人的な家族情報を教えても大丈夫?
A3: 公開情報は問題ないけど、個人情報保護は最優先。家族のプライバシーや医療情報は必ず匿名化・同意取得を。分身AIの人格は「印象」を模倣することが目的であって、リアルな個人情報を丸ごと公開するわけじゃないんだ。
Q4: 準備しないライブスタイルはどうやってスケールできますか?
A4: ライブの即興性は武器だけど、スケールするなら「テンプレ」と「要点のフォロー」を組み合わせると良い。ライブ→要点まとめブログ→分身AIへの学習ループという流れを作れば、同じ話を複数チャネルで再利用できるようになる。
Q5: 次の本についてもう少しヒントは?
A5: 今回の本は「分身AI×共創」をテーマにした実践寄りの内容が中心。表紙もできているし、実例やワークシートを多く入れてます。詳細は来週またちゃんとお知らせしますね。
📌 最後に:私のスタンスとこれからの約束
私は「3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEO」として、実務的に分身AIを作ってきた経験と、人生で培った転機(借金、ダイエット、がんの早期発見など)を武器に、埋もれた才能を応援したいと思ってるんだよね。
今日のライブみたいに寝坊してしまうこともあるけど、それも含めて僕の発信は等身大でいたい。失敗やトラブルは逆にコンテンツであり、学びだ。もしあなたが経営者や個人事業主で、忙しくて準備する時間がないなら、分身AIを活用して「あなたが頑張らなくても回る仕組み」を一緒に作ろうよ。

(動画タイムスタンプ参照: https://www.youtube.com/channel/UCEzawhU9T9apnRMLJBd3e4Q?t=613s)
来週はしっかり6:30から「おはようございます」を言います。次回は新刊の詳細や、もっと具体的な「共感ストーリー」テンプレの解説、そして分身AIを短期間で立ち上げるためのミニワークショップも考えてます。どうぞ楽しみにしててくださいね。ではまた。
— 田中啓之(分身AIひろくん)
GPTs研究会はこちら! |
|
無料!AI最新情報コミュニティ |
今すぐGPTs研究会をチェック! |






