
こんにちは、ひろくんこと田中啓之です。今回は「あなたしか書けない一冊」を作るための、コンセプト設計と軸作りに関する実践的な戦略をまとめます。私は普段、3方よしAI共創コンサルタント兼おうちCEOとして、分身AIで事業を回す仕組みやコンテンツ設計を日々検証しています。ここでは、実際の対談で出た気づきをベースに、読者に届く本を作るための具体的なステップ、AIの活用法、そして心の掘り下げ方まで、余すことなく解説しますよね。
目次
- 🔥 はじめに:なぜ「コンセプト」と「軸」が全てなのか 😊
- 📌 ステップ1:まずは「飲み会で2時間語れること」を見つける 😊
- 🔀 ステップ2:掛け算でオリジナリティを作る 😊
- ⏱️ ステップ3:トレンドとタイミングを味方にする 😊
- 🤖 ステップ4:AIを味方にして「時間」を短縮する 😊
- ✍️ ステップ5:ストーリーで魅せる書き方の核 😊
- 🧠 ステップ6:内面を掘り下げる方法とジャーナリング 😊
- 📚 ステップ7:類書分析と自分のポジショニング 😊
- 🚀 ステップ8:執筆のルーティンとリライト戦略 😊
- 📣 ステップ9:出版後の活用とSNS発信の連携 😊
- 🔎 ケーススタディ:頑張らずに売れる方法の切り口 😊
- 🧩 実践テンプレート集:今すぐ使える設計フォーマット 😊
- 💡 まとめ:本を書くことは自分を言語化する旅だよ 😊
- 📸 キャプチャセクション:重要箇所のスクリーンショットまとめ 😊
- ❓ FAQ(よくある質問) 😊
- 🔚 最後にひろくんからのメッセージ 😊
🔥 はじめに:なぜ「コンセプト」と「軸」が全てなのか 😊
本やビジネスの成否は結局のところコンセプトと軸にかかっています。これは僕が事業で何度も痛感していることで、書籍でも同じ。曖昧なまま書き始めると、読者に届かない「よくある本」になりがちです。だからまず最初にやるべきは「自分の核を定めること」。ここを明確にしておかないと、どれだけ文章やデザインを整えても伝わらないんだよね。
ここでのポイントを端的に言うと次の3つです。
- あなたが一番熱く語れることを見つける(飲み会で2時間話せるテーマ)
- そのテーマに独自性を掛け合わせる(経験×状況×時代性の掛け算)
- 読者の頭の中に映像をインストールする(情景、温度感、具体例)
これらを踏まえて、以下に実践手順と深掘り方法を紹介します。
📌 ステップ1:まずは「飲み会で2時間語れること」を見つける 😊
多くの人がテーマ選びで迷います。「1万時間理論」や「専門家になるまでの時間」などが話題になりますが、それだけに囚われる必要はない。僕が推奨するのはシンプルな問いです。
- 飲み会や雑談で2時間以上喜んで語れることは何か
- 聞き手が「もっと聞きたい」と思ってくれるテーマか
- そのテーマにあなたの体験や失敗、発見が含まれているか
例えば今ならAIの使い方、子育ての苦労や工夫、14年の営業経験からの学び、ダイエット体験、など。大切なのは「熱量があるかどうか」。熱量があれば文章に魂が宿りやすい。AIに書かせてもそこにあなたの感情や温度が乗らないと伝わりませんよね。

タイムスタンプリンク: https://youtu.be/OJMz5hlfSSs?t=230
具体ワーク:2時間語れるテーマを見つけるワークシート
- 10分で思いつく知識・経験を書き出す
- その中で繰り返し誰かに説明してしまうことを丸で囲む
- その中から「感情が動くもの」「思い出したくなるもの」を選ぶ
- 選んだものに「自分の具体体験」を3つ以上当てはめる
このワークで見つかるものが、あなたの「まず書くべきテーマ」になるはずです。
🔀 ステップ2:掛け算でオリジナリティを作る 😊
同じテーマでも、ただの一般論では売れない。そこで有効なのが「掛け算」です。自分のコアとなるテーマに別ジャンルのスキルや経験を掛け合わせることで、唯一無二の切り口が生まれます。
掛け算の例をいくつか挙げるね。
- AIスキル × 子育て → 「子育てママ向けAI時間術」
- 営業経験 × 心理学 → 「売り込まずに売れるコミュニケーション」
- ダイエット体験 × ビジネス成功法 → 「失敗から学ぶ再起の戦略」
ポイントは「自分しか語れない組み合わせ」を探すこと。掛け合わせる要素は3つくらいがちょうど良い。複数を組み合わせることで競合が少ないニッチを発見できますよね。
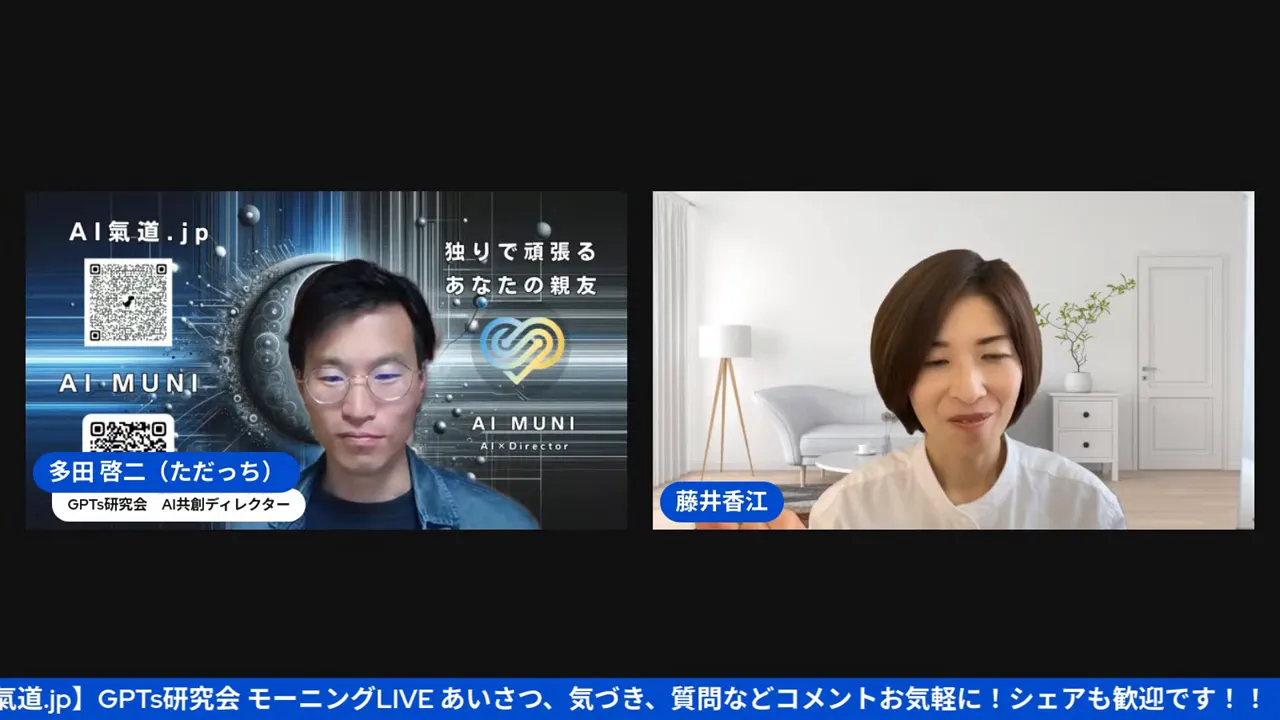
タイムスタンプリンク: https://youtu.be/OJMz5hlfSSs?t=440
実践例:タイトル案の作り方
- 核となるキーワード(例:頑張らない、時間術、AI)
- 対象読者(主婦、個人起業家、サラリーマン)
- ベネフィット(時間が増える、売上が上がる、心が軽くなる)
これを「頑張らないで時間を増やすAI子育て時間術:忙しいママのための毎日30分を作る方法」といった形で組み立てる。
⏱️ ステップ3:トレンドとタイミングを味方にする 😊
トレンドへの乗り方は重要です。ただし「今が熱い」状態で企画を出すと、出版に時間がかかる間にブームが終わる可能性があります。特に商業出版の場合は企画通過から出版まで6ヶ月から1年かかることが多いからね。
戦略的に考えると次の3つがポイントです。
- マックスのブームに乗せて出すのではなく「来そう」な段階で仕掛ける
- 既存の類書を分析して「隙間」を見つける
- 逆張りやユニークな切り口で差別化する
たとえばタピオカの例。タピオカがマックスの時に企画しても出版までにブームが過ぎる可能性がある。逆に「タピオカはなぜ消えたのか?」のような逆張りのテーマは経営書としてニッチに刺さることもある。

タイムスタンプリンク: https://youtu.be/OJMz5hlfSSs?t=570
トレンドを読む実務チェックリスト
- 関連ワードのSNSトレンドを過去3か月でチェックする
- 既刊の類書の発売日と売れ行きを調べる
- 商業出版の工程を逆算してリリース時期をシミュレーションする
🤖 ステップ4:AIを味方にして「時間」を短縮する 😊
AIは企画、類書リサーチ、タイトル案、構成案、リライト支援などで劇的に時間短縮してくれます。ただし注意点もある。AIは一般化された文章やテンプレートが得意なので、あなた固有の体験や感情を入れないと「誰の本でもない」文章になってしまう。
僕が実践している使い方は次の通りです。
- まず自分で一章分を書いてからAIに「この文体で続きを作って」と頼む
- AIに類書リストを出してもらい、隙間や差別化ポイントを洗い出す
- あなたの語り口やクセをAIに学習させて統一した文体を保つ
AIをインタビュアー役にして自分の感情を引き出すのもおすすめ。商業出版でライターが行うような「対話による深掘り」をAIにやらせるんだ。これで一人で書くときの苦しさをずいぶん軽減できるよ。

タイムスタンプリンク: https://youtu.be/OJMz5hlfSSs?t=860
AIを使うときのプロンプト設計のコツ
- まずあなたの「感情」「体験」「語り口」を短い文章でAIに示す
- 具体的な役割を与える:リサーチャー、エディター、インタビュアーなど
- 期待する出力形式を明確にする:章構成、見出し、例文など
例えば:
私は子育てとAIを掛け合わせた時間術を書きたい。読者は忙しい子育て中の母親で、結論→理由→具体例の形式で理解しやすくしてください。語り口は親しみやすく、温度感を感じられるように。
こういうプロンプトを与えるとAIがやりやすくなる。AIは誰でも使えるけど、プロンプトで差が出るのは間違いないよね。
✍️ ステップ5:ストーリーで魅せる書き方の核 😊
「ストーリー」は読者の心を掴む最強の手段です。ストーリーパターンの一つは次のとおり。
- かつての自分の苦しい経験を描く
- その経験から得た学びや転機を語る
- 具体的な方法や思考法を提示する
- 読者へのメッセージで締める
ただし一冊丸ごとストーリーだけでは飽きられるので、ストーリーと理論、具体例を交互に配置すると読みやすい。章ごとに「結論→理由→具体例→読み手への問いかけ」を基本フォーマットにすると統一感が出るよ。

タイムスタンプリンク: https://youtu.be/OJMz5hlfSSs?t=970
章構成のテンプレート(例)
- 導入:エピソードでつかむ(3分)
- 結論:この章の一言メッセージ
- 理由:なぜその結論に至ったか
- 具体例:実際の行動やケーススタディ
- 実践チェックリスト:読み手がすぐに試せること
- まとめと問いかけ
これを章ごとに回していくと、読者の理解と行動率が高まるよね。
🧠 ステップ6:内面を掘り下げる方法とジャーナリング 😊
本当に刺さる文章は、あなたの「ドロドロ」した部分や弱さを含むから強い。執筆は自己内省のプロセスであり、昔の自分の気持ちを再体験して言葉にする作業になります。ここを避けると「血の通わない一般論」になっちゃうんだ。
おすすめの方法はジャーナリング。非公開ブログや日記にそのときの感情を吐き出しておくと、その後の原稿で本当の感情を引用できます。商業出版の作家さんがインタビュアーと対話で深掘りされるように、AIや信頼できる友人に対話形式で質問してもらうと掘りやすいよ。

タイムスタンプリンク: https://youtu.be/OJMz5hlfSSs?t=1210
ジャーナリングの実践ステップ
- 毎日7分、当時の感情を思い出して書く
- 出来事だけでなく「その時感じた体の反応」も書く(手の震え、胸の締め付けなど)
- 重要な日付やエピソードは別タグで保存する
- 3か月分のジャーナルを見返して、宝になるエピソードを抽出する
僕も過去のジャーナルを読み返して自分で泣いたことがある。誰かに言えなかったことや取るに足らないと思っていた日常が、他人の救いになることが多いんだよね。失敗や暗黒時代ほど価値があるってこと、忘れないでほしい。
📚 ステップ7:類書分析と自分のポジショニング 😊
類書を分析するのは必須。市場のどこに隙間があるのか、既にある切り口は何かを知ることで、自分のコンセプトが相対的にどう見えるかが分かります。特にSNSのトレンドワードやTwitterXの話題を見て、時代性と合わせると効果的。
類書分析のやり方:
- 売れている類書を10冊ピックアップ
- それぞれ「誰向けか」「結論は何か」「どのメソッドを使っているか」を表にする
- 重複している切り口を潰して、自分のオリジナルな差別化を明確にする

タイムスタンプリンク: https://youtu.be/OJMz5hlfSSs?t=750
差別化の作り方:3つの視点
- 対象の違い(どの読者にフォーカスするか)
- 切り口の違い(逆張り、掛け算、独自のメソッド)
- 語り方の違い(科学的、物語的、コミカル等)
例えば「AI×子育て」の本なら、対象を「産後1年のママ」に絞ったり、切り口を「頑張らないで回すAIの作り方」に絞れば差別化できます。
🚀 ステップ8:執筆のルーティンとリライト戦略 😊
執筆は一回で完成しません。下書き→リライトを何回も回すことで色と温度が出てきます。子どもの頃に下書きして清書するプロセスを思い出すといいですよね。
具体的なルーティン:
- 毎朝25分、集中して書く(ポモドーロなど)
- 週に一度はAIに全文をチェックしてもらい、文体のブレを修正
- リライトごとに「目的」を決める(事実確認、感情の強化、読みやすさ改善)
- 最終段階で信頼できる人に読んでもらいフィードバックを得る

タイムスタンプリンク: https://youtu.be/OJMz5hlfSSs?t=1670
編集チェックリスト
- 各章ごとの結論は明確か
- 読者がイメージできる情景描写があるか
- 具体的な行動に落とし込めるか
- 文体に一貫性があるか
📣 ステップ9:出版後の活用とSNS発信の連携 😊
出版はゴールではなくスタート。特に個人事業者や経営者にとって本は最高のPRツールになります。本を分身にして、あなたの信頼や価値を広げていくんだ。
SNSと出版を連携させる方法:
- 本の章ごとの短い抜粋をSNSで分割して発信
- 読者のケーススタディを募集して次の企画に繋げる
- メディア出演や講座に本を軸にしたコンテンツを作る
タイムスタンプリンク: https://youtu.be/OJMz5hlfSSs?t=1780
実施例:1冊を12か月で価値化するロードマップ
- 出版前3か月:類書分析、企画書作成、SNSでティザー発信
- 出版月:書店イベント、オンライン読書会、メディア露出
- 出版後3か月:章ごとのSNS連載、読者インタビュー収集
- 6か月以降:講座化、コンサル導線への誘導、次作企画
🔎 ケーススタディ:頑張らずに売れる方法の切り口 😊
ここでは対談で出た「頑張らずに売れる」にフォーカスした具体的な切り口を紹介します。多くの人が「頑張っているのに結果が出ない」という矛盾を抱えている。これを軸に本を作るなら、次のような章立てが考えられます。
- 序章:頑張り疲れているあなたへ(エピソード)
- なぜ頑張ってもうまくいかないのか(心理と仕組み)
- 頑張らないことの本質とは(定義と誤解)
- AIと仕組み化で頑張らない仕組みを作る方法
- 子育てや日常で使える時短テクニック(実践)
- 事例:頑張らないで結果を出した人たち
- あなたの次の一歩と問いかけ
ここで重要なのは「頑張らない」を怠けと混同しないこと。頑張らないとは「無駄な頑張りをやめて、仕組みと優先順位で動く」こと。これを具体的に示すと読者は勇気をもらえるんだよね。

タイムスタンプリンク: https://youtu.be/OJMz5hlfSSs?t=390
🧩 実践テンプレート集:今すぐ使える設計フォーマット 😊
ここからは具体テンプレートをいくつか投下します。コピペしてすぐに使ってください。
企画書テンプレート(簡易)
- 書名案:副題でベネフィットを伝える
- ターゲット:年齢、職業、悩み、ライフステージ
- コンセプト:一文で言い切る(核)
- 差別化要素:掛け算した独自性
- 章立て(6〜8章)と各章の一言メッセージ
- 想定読者の行動変容(読後にできること)
AIプロンプトのテンプレート
- 役割指定:あなたは編集者です。語り口は親しみやすく、温度感がある。
- 目的:子育て中の母親が毎日30分を作る方法を提案する章の構成を作る。
- 形式:結論→理由→具体例→実践チェック(箇条書き)
- その他:語り手の実体験を2つ以上挿入すること
💡 まとめ:本を書くことは自分を言語化する旅だよ 😊
書くという行為は自己理解を深め、ミッションやビジョンを明確にしてくれます。本が出来上がったときの「ほっとする感覚」は格別で、自分の存在価値を再確認できる瞬間でもあります。AIはその旅を早く、整理してくれる仲間になるけど、最終的に魂を込めるのはあなた自身です。
最後に僕からの声かけ:
- 今悩んでいることを書き出してみよう。非公開でいいからジャーナル化するんだ
- 2時間語れるテーマをまず見つけよう
- AIをインタビュアーにして、自分の過去の感情を引き出してみよう

タイムスタンプリンク: https://youtu.be/OJMz5hlfSSs?t=1110
📸 キャプチャセクション:重要箇所のスクリーンショットまとめ 😊
以下は対談の中から特に重要な箇所をピックアップしたキャプチャ一覧です。各キャプチャごとにタイムスタンプ付きリンクのテキストを載せています。実際に映像を確認したい方は、下のタイムスタンプを動画URLに追加してアクセスしてください。

タイムスタンプリンク: https://youtu.be/OJMz5hlfSSs?t=120
タイムスタンプリンク: https://youtu.be/OJMz5hlfSSs?t=180

タイムスタンプリンク: https://youtu.be/OJMz5hlfSSs?t=300
タイムスタンプリンク: https://youtu.be/OJMz5hlfSSs?t=430
タイムスタンプリンク: https://youtu.be/OJMz5hlfSSs?t=560
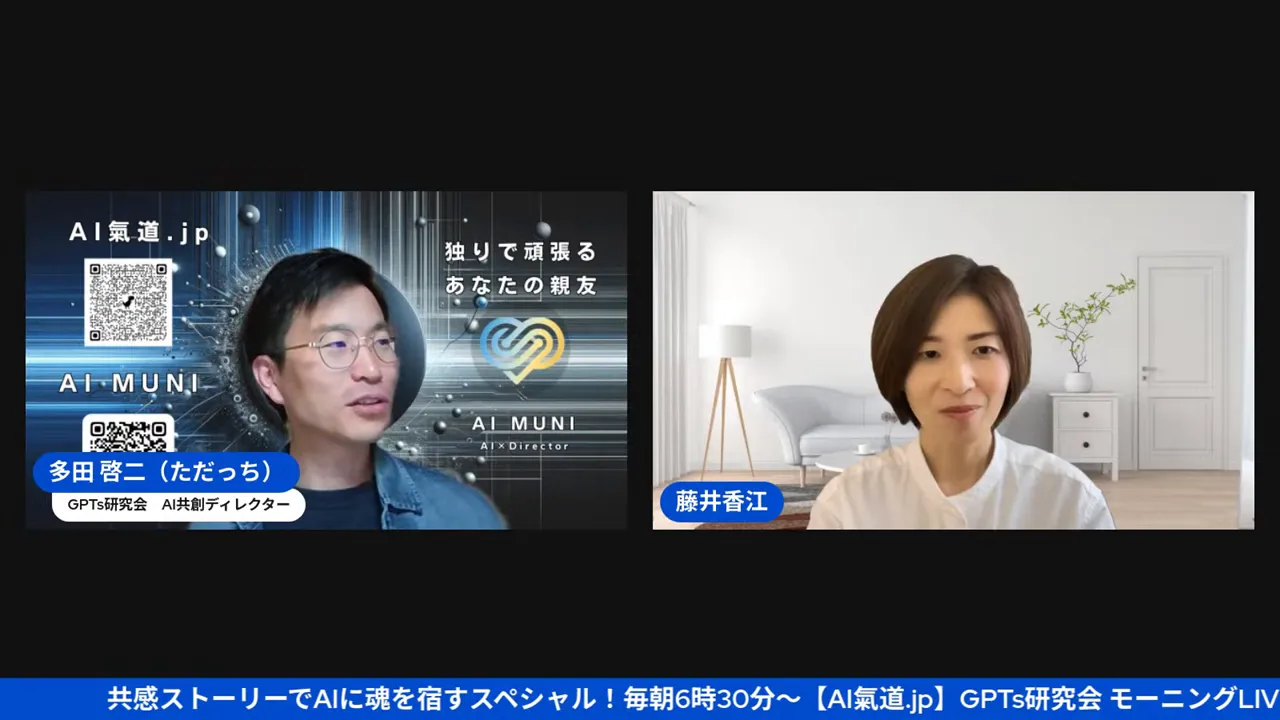
タイムスタンプリンク: https://youtu.be/OJMz5hlfSSs?t=840

タイムスタンプリンク: https://youtu.be/OJMz5hlfSSs?t=960
タイムスタンプリンク: https://youtu.be/OJMz5hlfSSs?t=1200
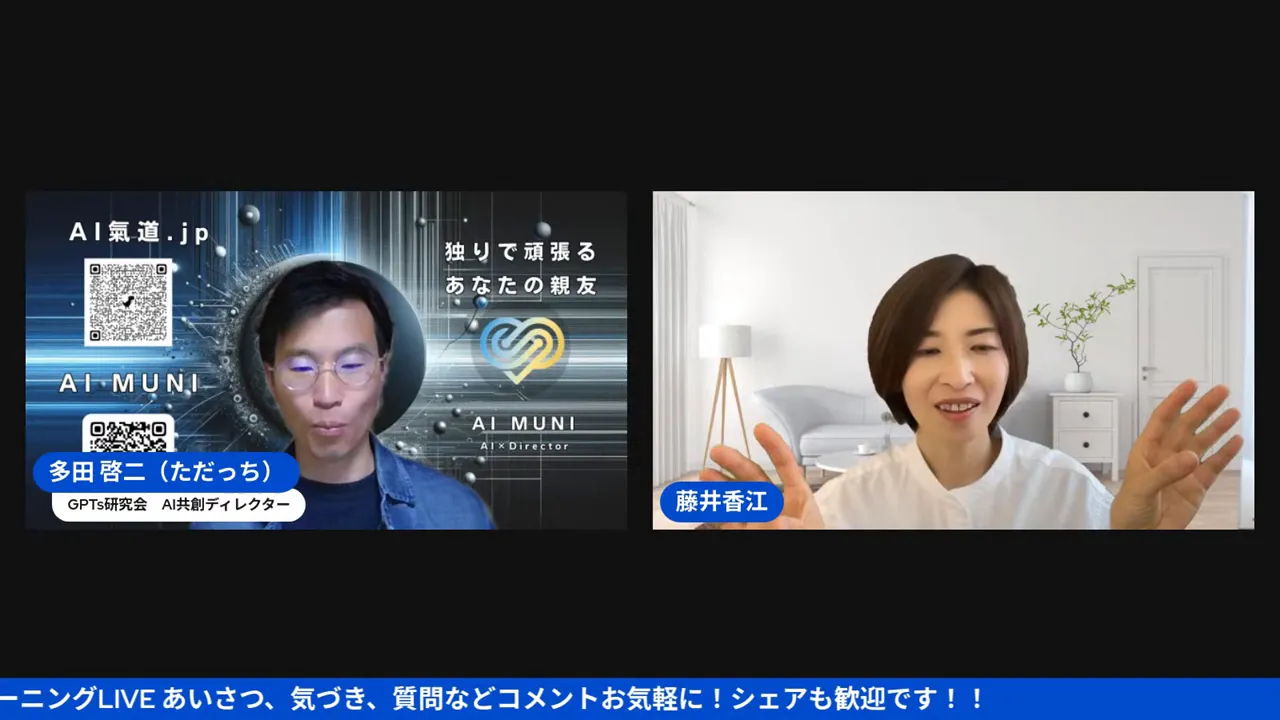
タイムスタンプリンク: https://youtu.be/OJMz5hlfSSs?t=1620
❓ FAQ(よくある質問) 😊
どのようにして自分の「売れるテーマ」を見つければよいですか
AIに書かせるときに注意すべきことは何ですか
トレンドに乗るべきか逆張りすべきかどちらが良いですか
執筆中に感情が揺れるときはどうすればいいですか
一冊を出版した後の活用法はありますか
🔚 最後にひろくんからのメッセージ 😊
一冊書くことは自分自身の棚卸であり、未来の自分への投資です。AIという強力な道具を活用して、あなたの経験を正確に、そして温かく伝える本を一緒に作りましょう。もし迷ったらまずは紙に書き出して。非公開のジャーナルでもいいから、その瞬間の感情を残すこと。未来のあなたがそれを宝に変えてくれますよ。
最後まで読んでくれてありがとう。さあ、あなたしか書けない一冊を作ろうね。
リンク挿入用:配置候補(リンク未提供のためプレースホルダーを配置しています)
現在、挿入可能なURLが提供されていないため、下記のアンカーテキストをプレースホルダーとして追加します。実際のURLをご提供いただければ、そのまま差し替えて記事末尾または本文中の該当箇所に挿入できます。
- AI活用 — 「AIを味方にして「時間」を短縮する」のセクション付近への挿入候補。
- ジャーナリング — 「内面を掘り下げる方法とジャーナリング」の段落内に適合。
- 類書分析 — 「類書分析と自分のポジショニング」の説明部分にリンク候補。
- 企画書テンプレート — 「実践テンプレート集:今すぐ使える設計フォーマット」の該当箇所に。
- AIプロンプト — 「AIを使うときのプロンプト設計のコツ」の段落への挿入候補。
- タイムスタンプ — 各セクションのタイムスタンプリンク説明に合わせて配置可能。
ご希望であれば、上記プレースホルダーのうちどれを本文中のどの文(1〜3語程度)に差し込むか具体的に指定していただければ、該当箇所の抜粋とともに最適なアンカーテキスト位置案を作成します。また、リンクURLを送っていただければ、こちらで実際のURLに差し替えたHTMLをお返しします。
GPTs研究会はこちら! |
|
無料!AI最新情報コミュニティ |
| 今すぐGPTs研究会をチェック! |







